PR ※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
「特養に入ったからもう安心」と思っても、高齢者の体調は変わりやすく、病気やケガで入院になることは珍しくありません。
その時にご家族様から必ず聞かれるのが「入院したら特養の部屋はどうなるの?」「退院後も戻れるの?」という不安です。
実は「3ヶ月ルール」という言葉も耳にしますが、これは国が定めた制度ではなく、施設ごとの運営規定で決められているものです。
この記事では、特養入居者が入院したときの実際の流れと注意点を、元相談員の立場からわかりやすく解説します。
特養入居者が入院したときの基本的な流れ
⚫︎状態が早く回復した場合:退院後に元の特養へ復帰できる可能性が高い
⚫︎状態が悪化した場合:医療依存度が高まり、介護医療院や医療機関系の施設への転院が検討される
⚫︎入院が長引いた場合:施設ごとのルールで「ベッドを空けておけるのは◯ヶ月以内」などと定められており、その期間内に戻れなければ退去扱いとなり、在宅に戻る可能性もある
このような事情から「3ヶ月ルール」という表現が通例になっているのです。
「3ヶ月ルール」とは何か?

特養に関わるご家族からよく聞かれるのが「3ヶ月入院すると退去になる」という話です。
結論から言えば、「3ヶ月で強制退去」と国が定めているわけではありません。
実際の根拠となっているのは、厚生労働省が定める「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」第22条です。
引用:厚生労働省「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」第22条
特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
条文が本来示していること
この条文が示しているのは
「3ヶ月以内なら退院後に円滑に戻れるよう支援するべき」
という趣旨であり、入居者を守るための規定です。
国の意図としては、病気やケガで一時的に入院しても、すぐに退去を迫るのではなく、戻れるよう配慮することを求めています。
現場での解釈とのギャップ
しかし実際の介護現場では、この条文が「3ヶ月を超えたら退去」と解釈されるケースが多く見られます。
背景には、特養が「満床でやっと採算がとれる」仕組みであることや、常に多くの待機者を抱えていることがあり、施設側としては長期間ベッドを空けておけない事情があるのです。
そのため「ルールだから仕方ない」とご家族に説明されることも少なくありません。
対応は施設ごとに異なります。
多くの特養は「3ヶ月以内なら復帰を保証する」としていますが、入院が長引いても家族との話し合いによっては延長が認められる場合もあります。
入居者本人の状態、施設の方針、ご家族との調整によって判断されるのが実情です。
厚労省の第22条はあくまで入居者を守るための規定であり、「3ヶ月経過=退去」という単純な仕組みではありません。
むしろ、この条文の本来の意図と、現場での受け止め方にギャップがあることを理解しておくことが重要です。
入院中の居室と費用

入院中でも払わなくてはいけない費用は
⚫︎居住費(家賃・管理費にあたる部分)
➡︎実際に住んでいなくても「部屋を確保している」ため、支払いが必要な場合が多い。
支払いの必要がない費用は
⚫︎介護サービス費・食費
➡︎食事の提供や、介護は受けていない(介護報酬分)は支払い不要となります。
つまり、入院中は「住んでいないのに家賃だけ払い続ける」状態になるのです。
ただし、対応は施設によって異なります。
私が働いていた施設では、特養の入院中のお部屋を(ご家族の了承を得られた場合に限り)、ショートステイの方にお貸しするというシステムがありました。入院中の荷物は基本的に動かさず、ベッドだけをお貸しするイメージです。
ショートステイの方の中には介護度が高く、ほとんどベッドで過ごされる方もいるため、このような方であれば、タンスを開けたり部屋の中を歩き回る心配はありません。
その間、入院中の方の居室管理費はかからなかったため、このシステムを了承されるご家族様がほとんどでした。
このように「入院中の費用負担」や「部屋の扱い」は施設ごとに運営方法が異なるため、必ず事前に確認しておくことが大切です。
退院後に戻れるケース/戻れないケース
戻れる場合
⚫︎入院期間が短い(数週間〜数ヶ月)
⚫︎入院前と大きく状態が変わらず、特養で対応可能な医療行為の範囲に維持できている
戻れない場合
⚫︎医療依存度が高くなった
例:頻回な痰吸引、胃ろう、点滴や輸血、在宅酸素濃縮器使用など
(施設ごとに対応できる範囲が異なる)
⚫︎要介護度が改善して、特養の入居要件(原則要介護3以上)を満たさなくなった
特養から別の特養に移れるのか?

「今の特養から別の特養へ移れますか?」という質問も時々あります。
結論から言えば、制度上は可能ですが、実際には非常に難しいと私自身は感じています。
なぜ難しいのか?
特養の役割は「生活が限界に近い人」を優先して入居させる施設です。
すでに特養に入居している時点で「居場所と介護をしてくれる人が確保されている」と判断されるため、介護のせっ迫性が低いとみなされ、新たに別の特養に入り直すことは極めて難しいのです。
移れるのは例外的なケース
- 家族の転居で、遠方に移動せざるを得ない場合
- 現施設での生活が著しく困難(虐待・医療対応が不十分など)の場合
- 入院を機に退去となり、他の特養に申し込む必要が生じた場合
これらの「特別な事情」がない限り、原則として特養から別の特養に移るのは難しいと言えます。
現場の実感
私が相談員をしていたときにも「家の近くに移りたい」という相談はありました。
しかし、待機者が何百人もいる中で「すでに特養に入っている人」が優先されることはほとんどなく、実際に移れたケースは例外的な事情があるときだけでした。
家族が入院時に確認しておくべきこと

①施設と病院に連絡を取り合う
→ 入院が決まったら、すぐに施設へ連絡。病状や入院期間の見通しを共有する。
②費用の確認
→ 居室料を払い続けるのか、一時的に免除されるのかを必ず確認。
ショートステイの方に貸す期間、居室代が免除されるなど特例がないか
③退院後の選択肢を考えておく
→ 状態によっては特養に戻れない可能性があるため、老健や介護医療院、有料老人ホーム、訪問医療で在宅復帰なども並行して情報収集しておく。
まとめ
⚫︎特養入居中に入院した場合、回復すれば復帰、悪化すれば介護医療院などへの転院になる
⚫︎入院が長引くと「3ヶ月ルール」など施設ごとの規定に従い、退去や在宅復帰になることもある
⚫︎籍を残す場合でも費用がかかるかどうかは施設ごとに異なる
⚫︎「3ヶ月ルール」は国の基準ではなく、あくまで施設運営上の通例
⚫︎家族としては、費用と退院後の選択肢を事前に確認しておくことが安心につながる
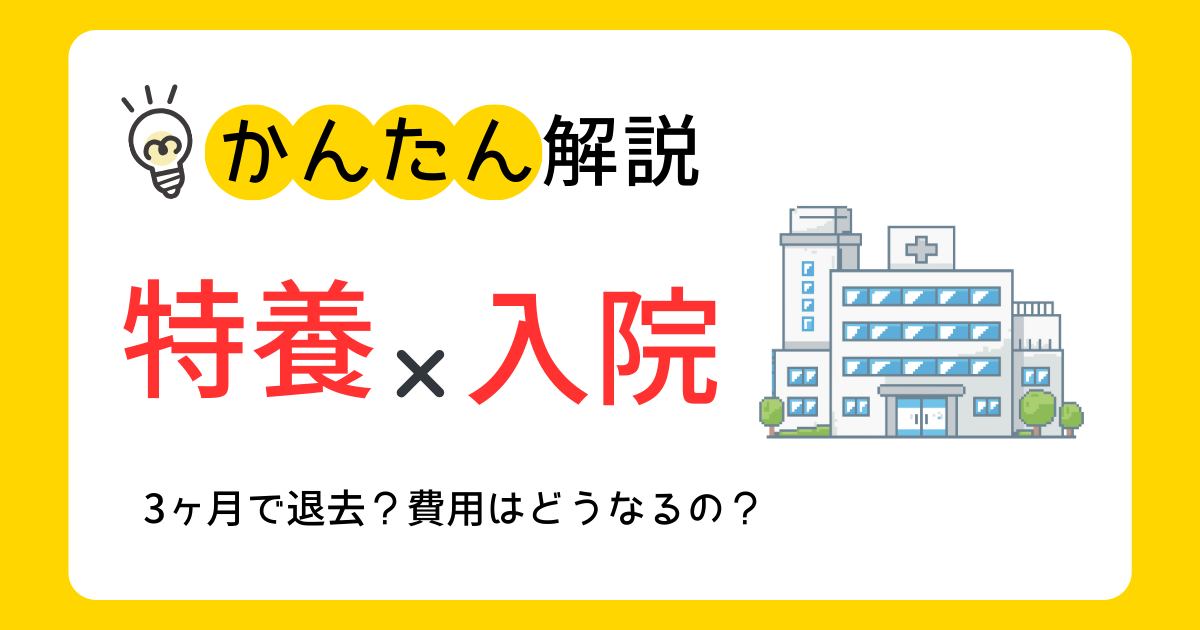
コメント