高齢者施設に入居していても「選挙に行けるのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
高齢者にとって選挙は、人生の集大成とも言える大切な自己表現の場。
しかし実際には、体の不自由さや環境の制限で投票機会が失われているケースもあります。
今回は、施設入居中の高齢者でも投票できる方法や、現場での工夫、課題について、現役の介護職としての視点も交えて解説します。
入居中でも投票はできる?
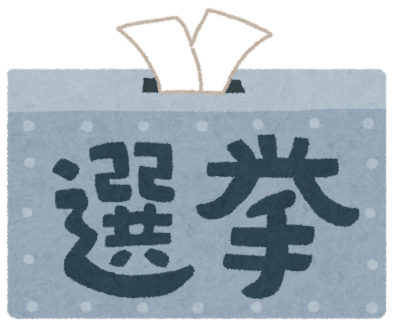
結論から言えば、施設に入居していても選挙権は失われません。
憲法に基づく基本的人権として、全ての国民に認められた権利です。
高齢者が投票する方法としては、主に以下の3つがあります
- 通常の投票所に出向く「通常投票」
- 自宅・施設から郵送する「郵便等投票」(要申請・要件あり)
- 施設内で投票できる「不在者投票制度」
この中でも最も利用されているのが、不在者投票制度です。自治体が施設に訪問し、その場で投票所を開設してくれるため、高齢者の負担が少なく済みます。
「不在者投票管理施設」とは?
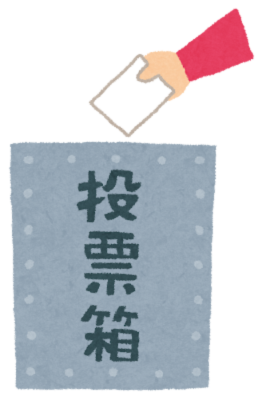
不在者投票を行うには、施設が「不在者投票管理施設」として自治体に登録されている必要があります。
この制度のメリットは:
- 高齢者が施設内で安心して投票できる
- 自治体職員が対応するため公正性が確保される
- 投票所への移動負担が不要
ただし、全ての施設が登録しているわけではありません。施設の方針や地域の対応状況によっては、不在者投票が実施されていないこともあります。
以前私が勤めていた施設では、ケアマネージャーが選挙の担当をしていました。
ご本人様やご家族様が依頼した方のみでしたが、毎回時間をかけて、どんな考えの候補者がいるのかを丁寧に説明して、ご本人様の意思の確認をおこない投票のお手伝いをしていました。
認知症があっても投票できる?
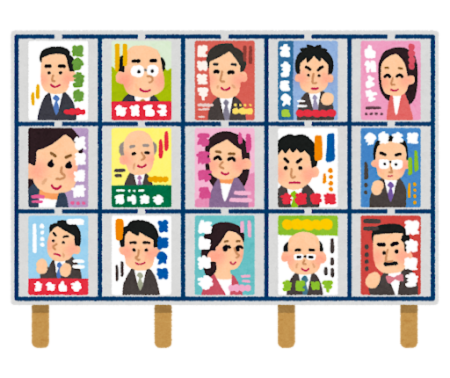
認知症のある方でも、意思表示ができる状態であれば投票は可能です。
厚労省も「本人が選択できる状態であれば、支援があっても投票は妨げられない」としています。
ただし、以下の点には注意が必要です:
- 職員や家族による過度な誘導はNG(選挙干渉)
- 代筆する場合は、本人の明確な意思に基づく必要がある
本人の「自分で選ぶ権利」を尊重しながらサポートすることが大切です。
実際の取り組みと施設での工夫
選挙時には、以下のような取り組みをしている施設もあります
・候補者の名前を見やすく掲示する
・投票の流れや仕組みを事前に説明する
・視覚・聴覚が弱い方には配慮した支援を行う
・情報伝達や記入サポートは2人1組で実施(公正性の担保)
また、地域によっては包括支援センターやボランティアが連携し、移動支援や制度の案内を行っているケースもあります。
実際には投票できない人も…その理由とは?
制度としては投票可能でも、実際には以下のような理由で「投票できない」ケースも少なくありません。
・施設が不在者投票に対応していない
・家族による送迎や付き添いが難しい
・施設職員の手が足りない
・本人の体調や意欲の問題
このように、制度以上に「環境」と「人手」が大きく影響しているのが現実です。
介護保険外サービスという選択肢
ご本人の意思はしっかりしているけど、家族も、施設も選挙投票所に連れて行ってあげられない。
そんな場合は介護保険外サービスに頼るという手もあります。
困った時にすぐにヘルパーを手配できて、施設へのお迎えや帰設、排泄介助に投票の記入サポートまでなんでもお任せできます。どんなサービスか無料で問い合わせするだけでもokです。
本当に使えるかサービスを受けてみました。⬇️
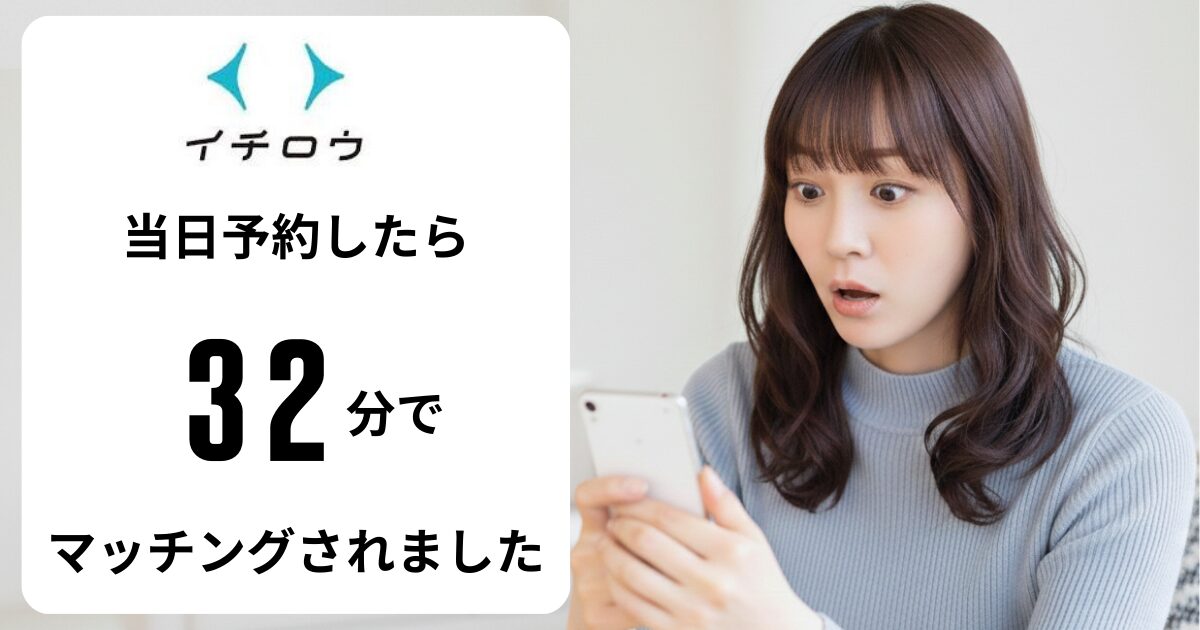
まとめ|選挙は“つながり”を実感するチャンス
高齢者施設に入っても、投票は可能です。 そして選挙は「誰に投票するか」よりも、「自分で選ぶ」という行為そのものが人生の証。
社会とのつながりを維持し、自己決定を支えることは、介護の質の向上にもつながります。
施設・家族・地域が連携し、高齢者が“最後まで社会の一員として声を届けられる仕組み”を作っていくことが求められています。
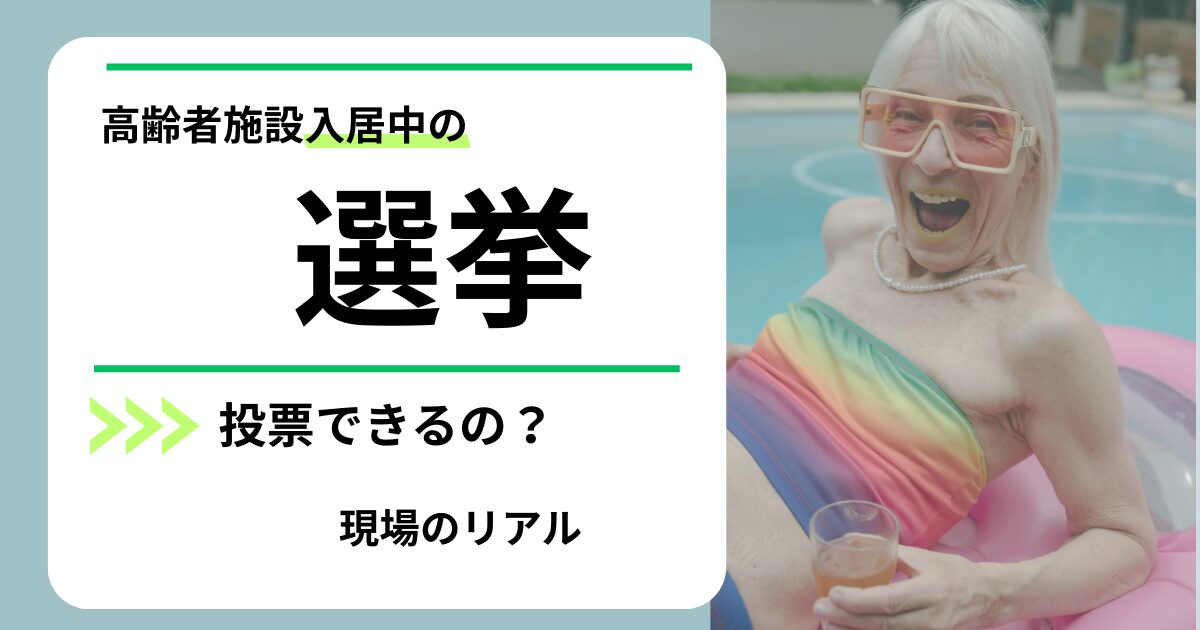
コメント