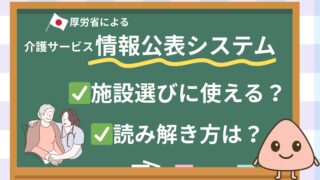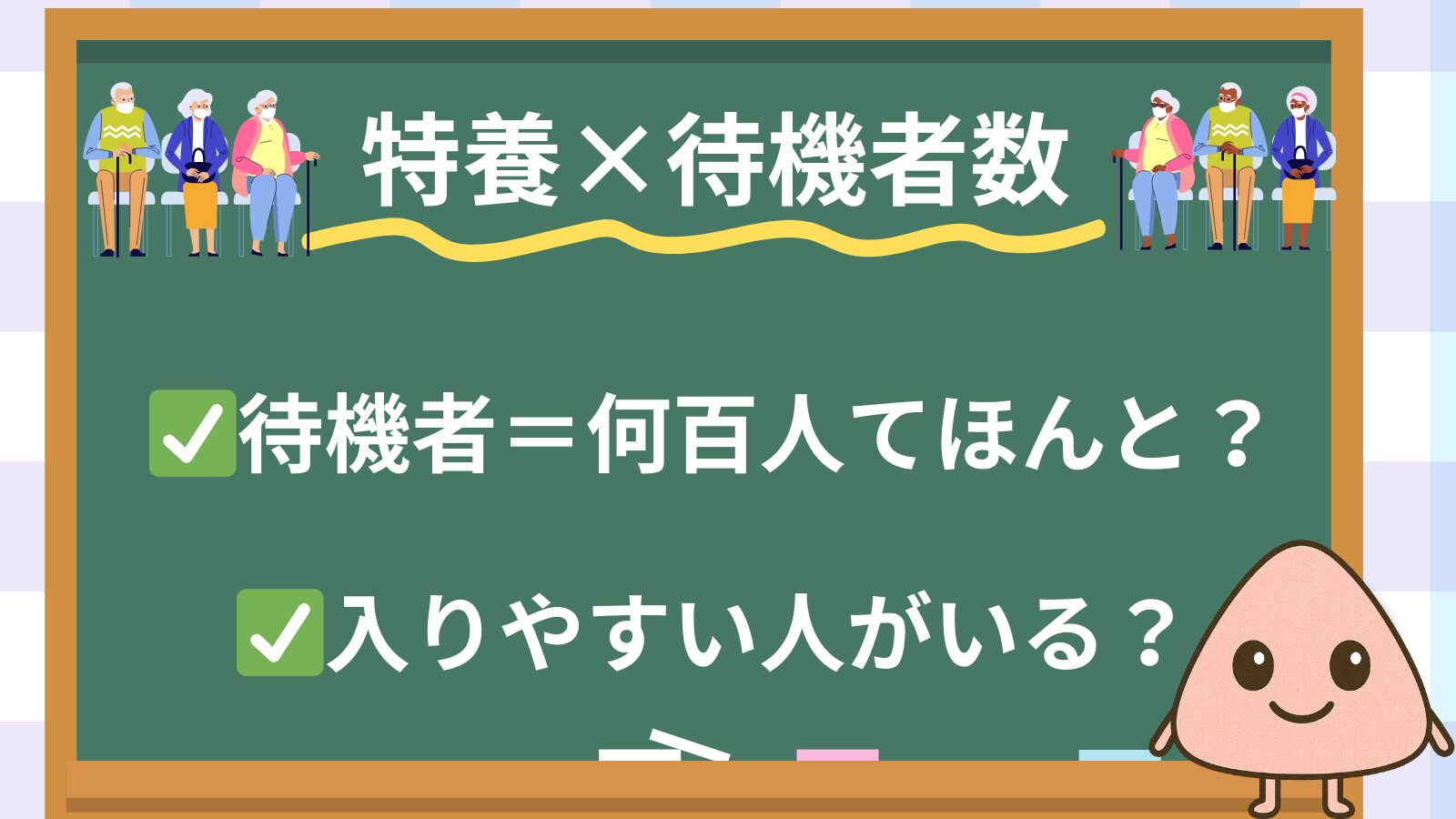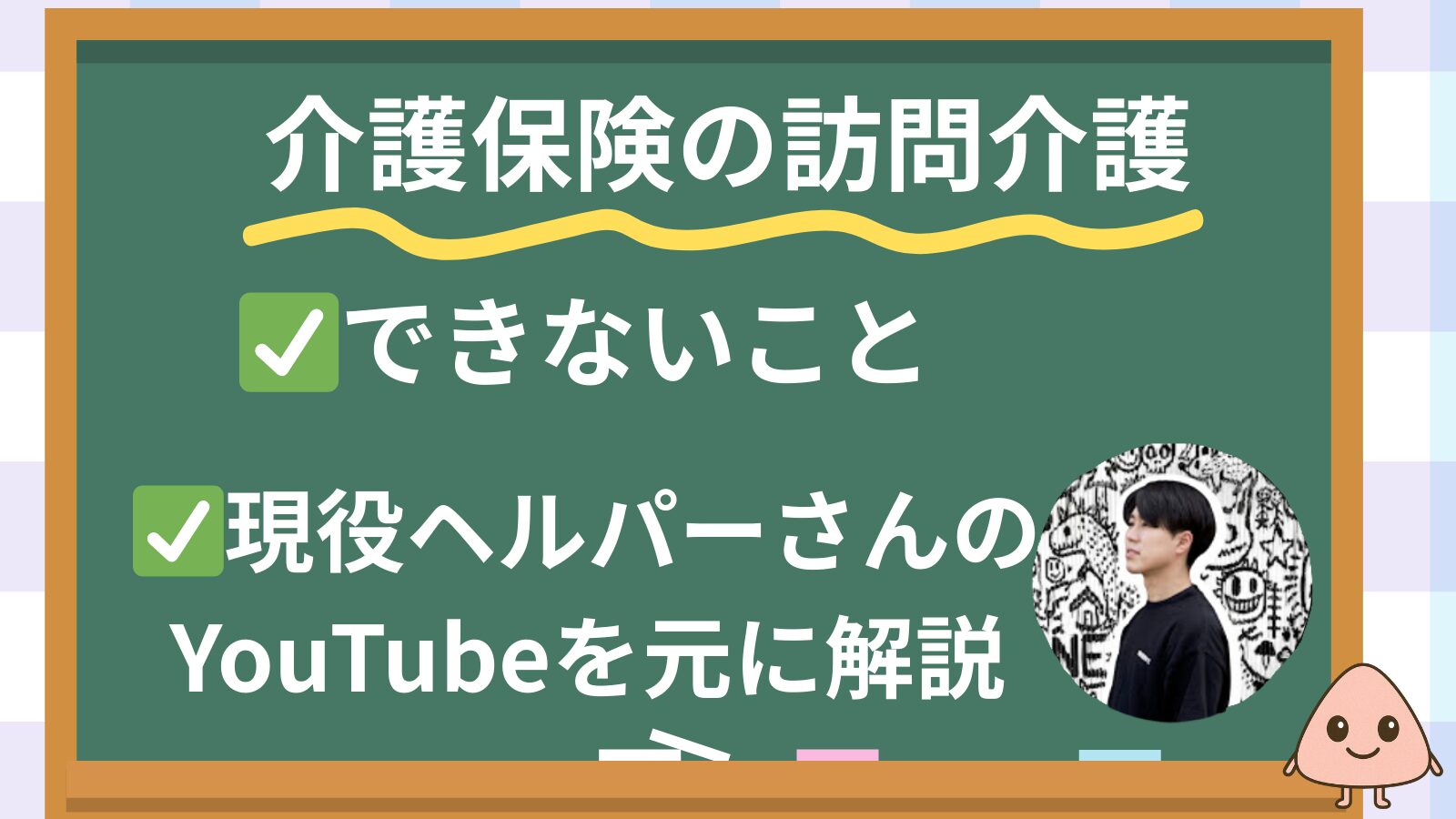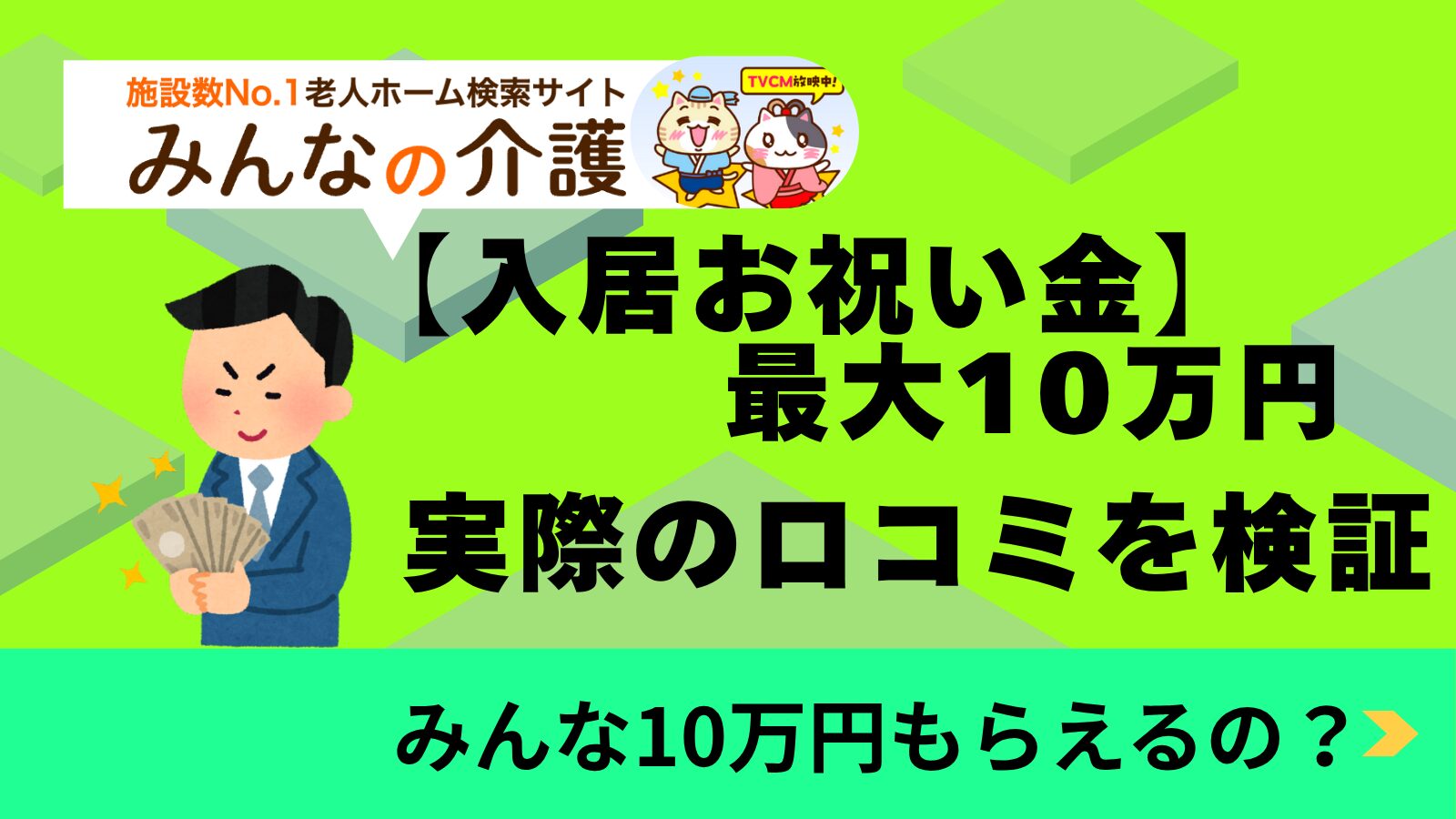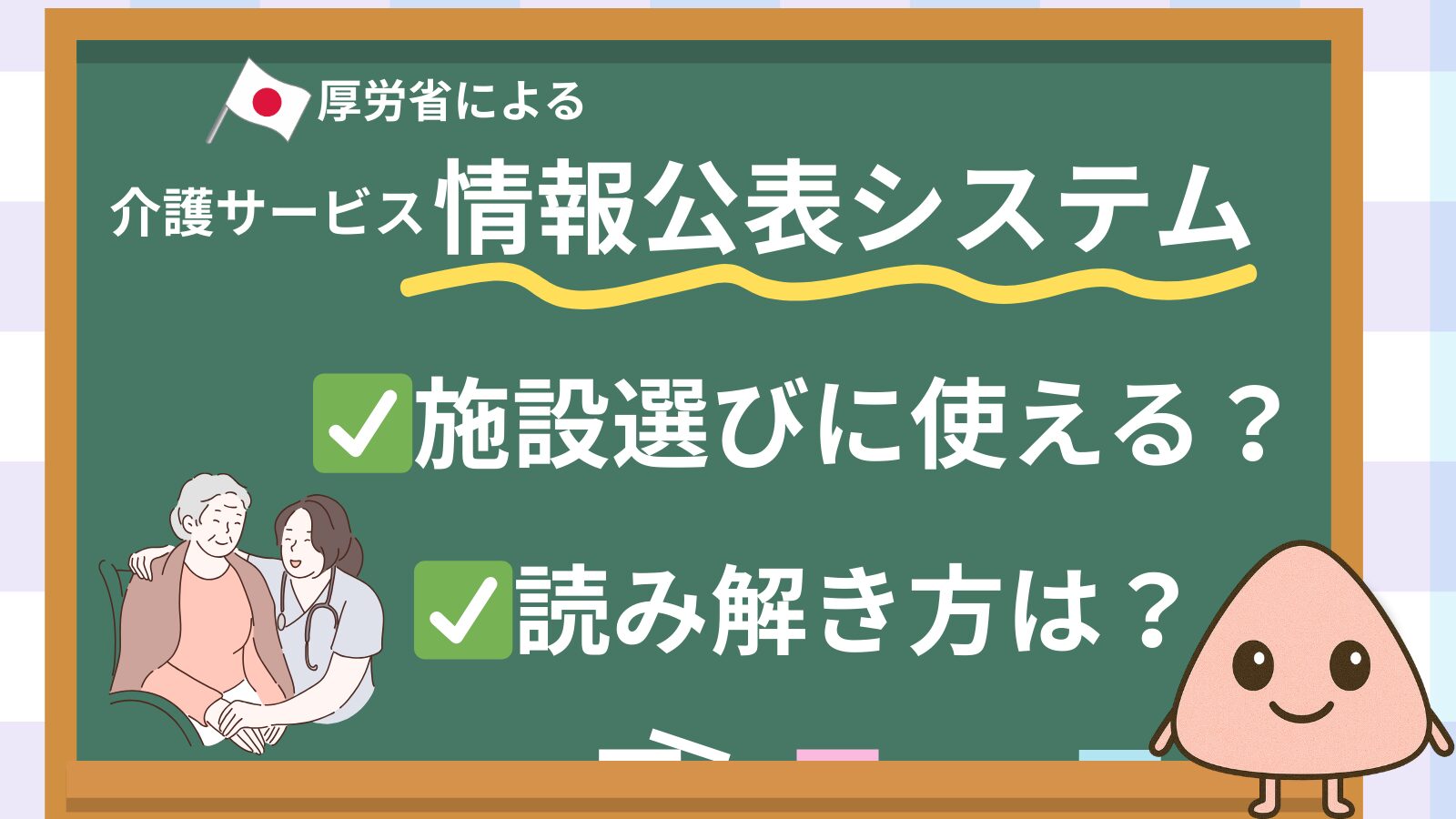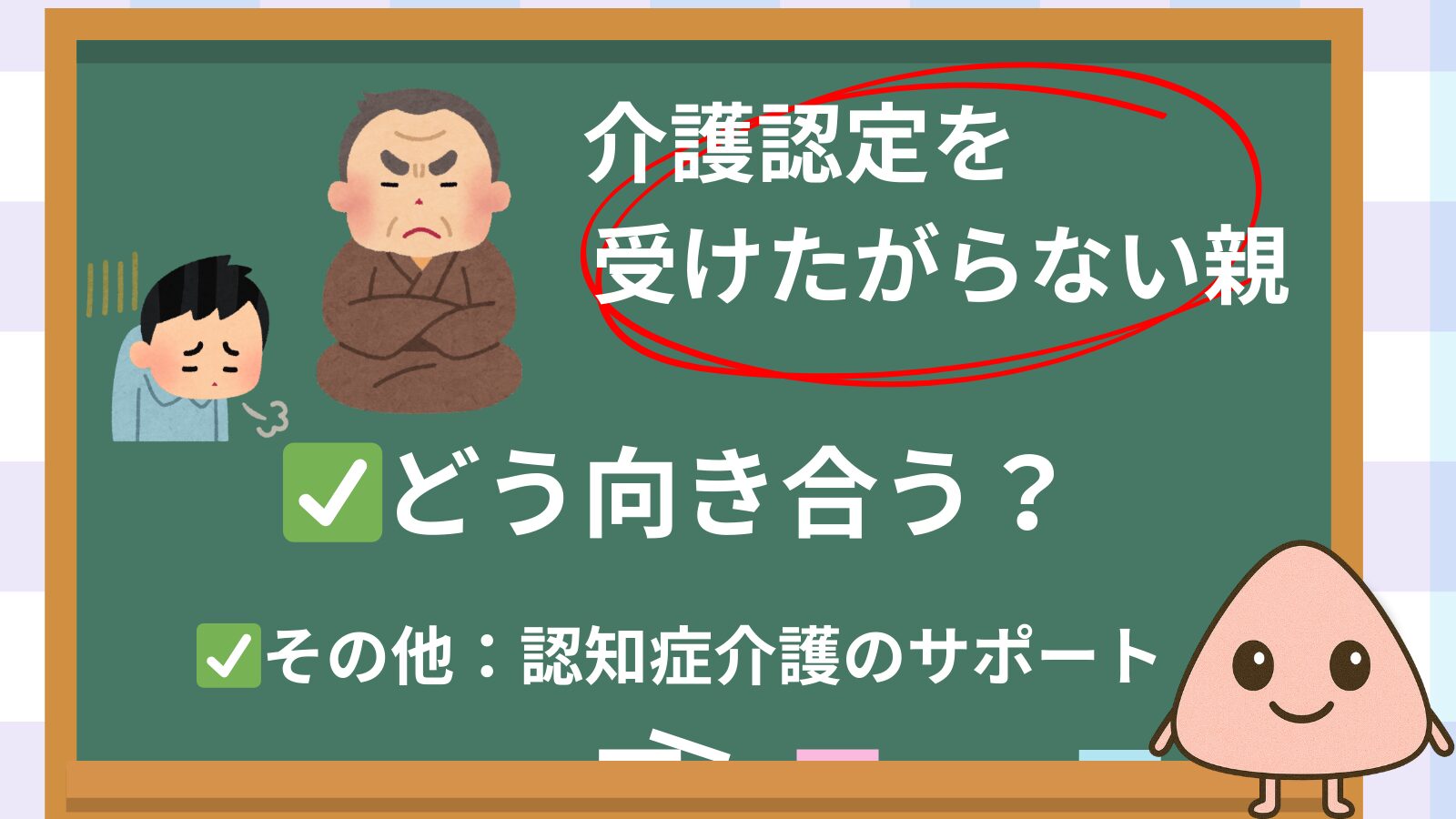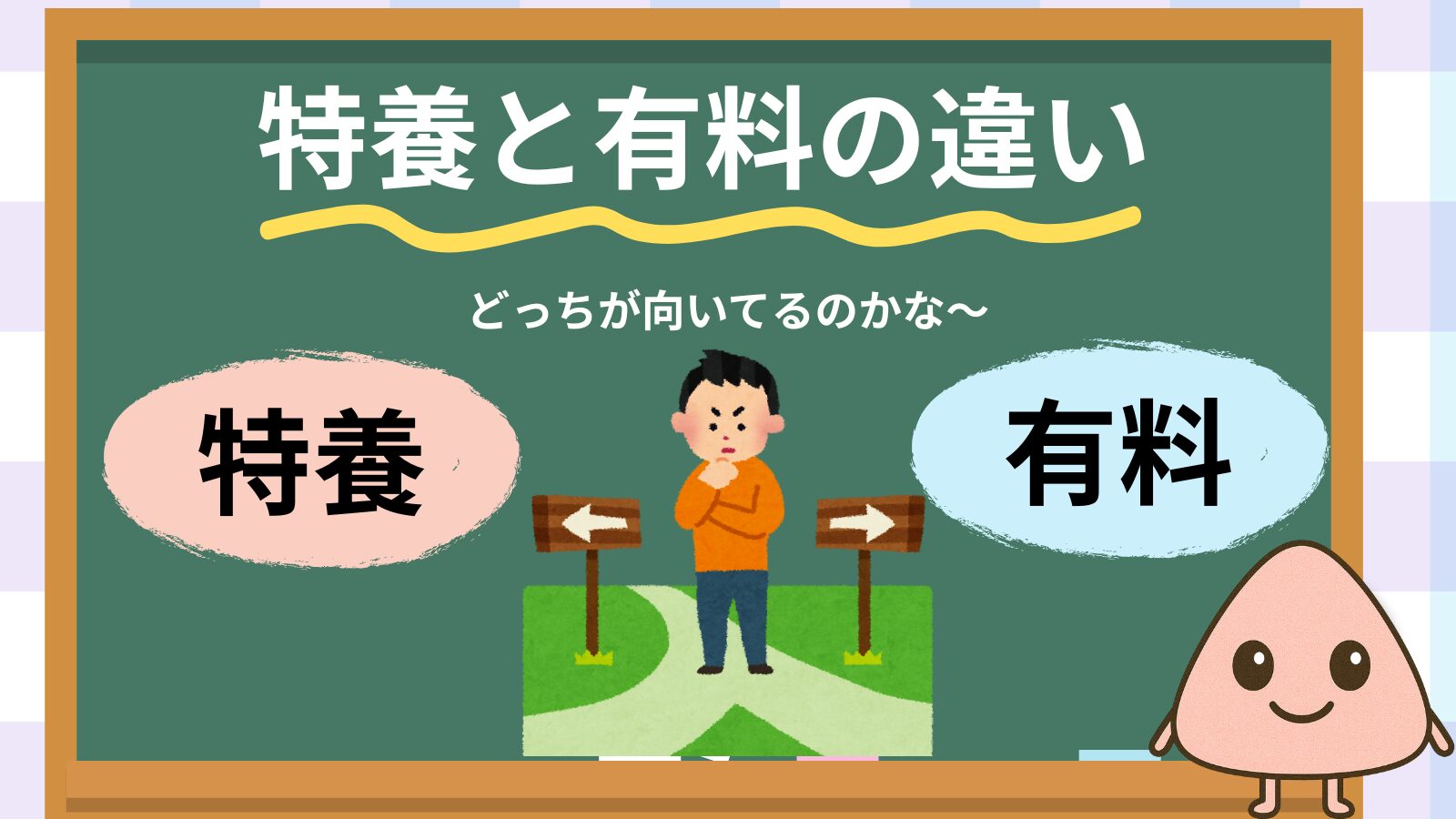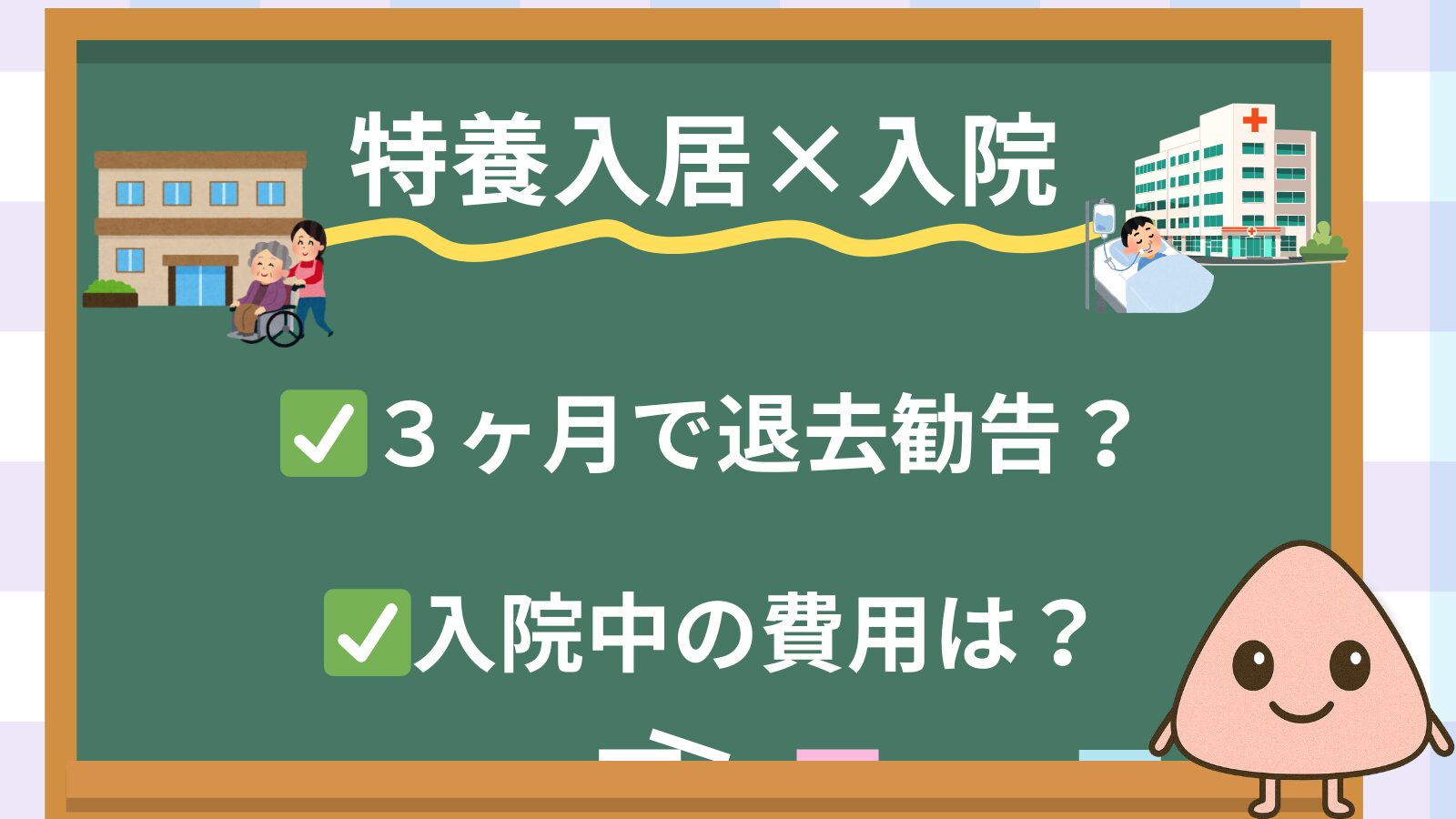入居後に後悔しない!介護施設の選び方と見学でチェックすべき3つのポイント
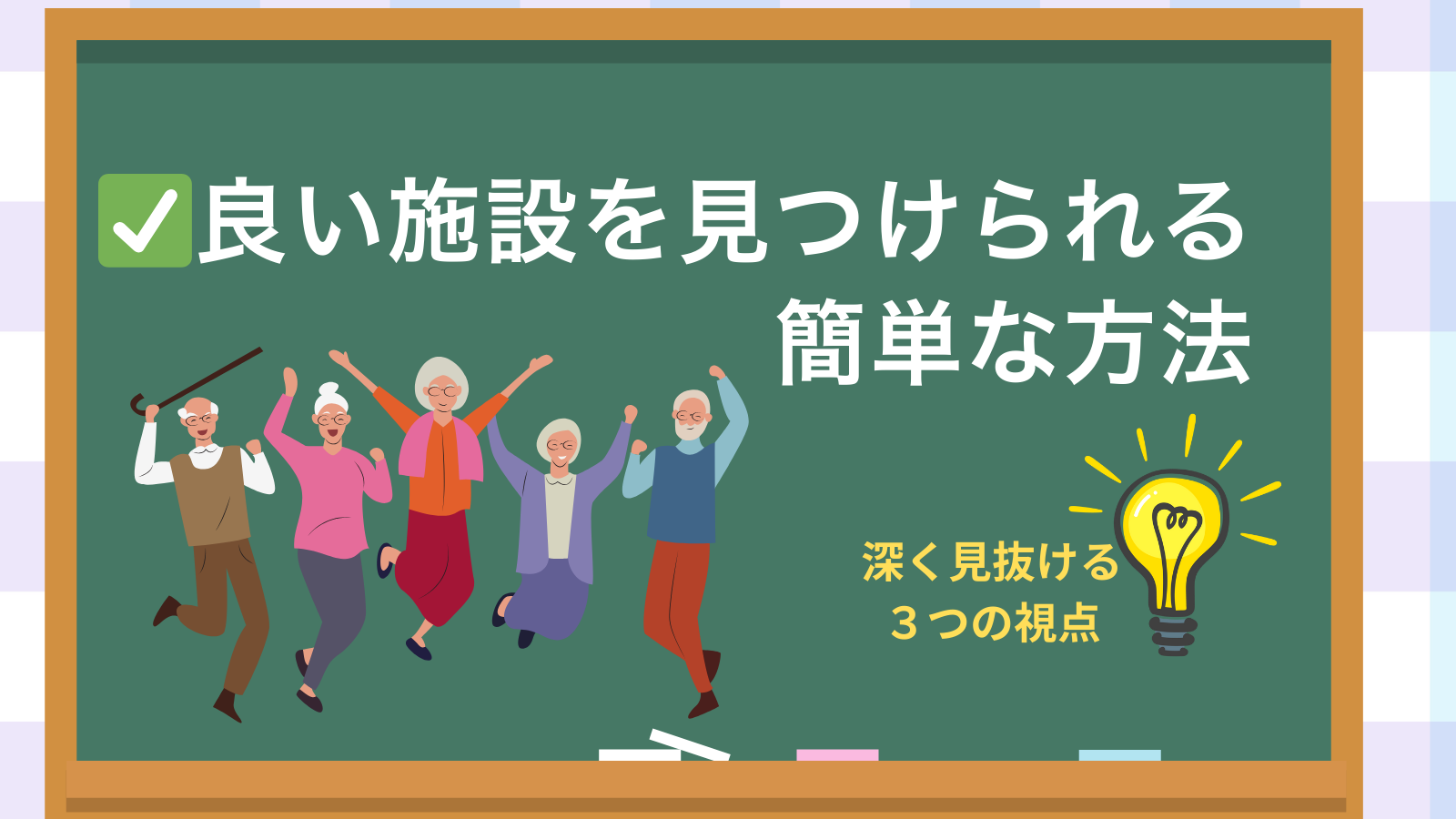

施設選びは始めたけど、何をどうやって比較すればいいんだろう?
とにかく安心して暮らせるホームに入れてあげたいし
ヤバい施設にだけは当たりたくないな
そんな風に感じていませんか?
この記事では、初めて施設を見学する方でも、簡単に施設を比較できる方法をお伝えします。
「ご本人様ファースト」の視点から、本当に合った施設を選ぶためのチェックポイントをまとめました。
☑️この記事でわかること
- 誰でも使える具体例とチェックリスト
- たった数分でも深く見抜ける3つの視点
- 施設選びの最初のステップ
誰でも”介護施設の良し悪し”を見抜けるチェックリスト!
| 入居者 | 肌の保湿 | 肌が乾燥していないか全体に確認 | ||
| 髪の毛 | 髪の毛が整っているか | |||
| 膝掛けや上着 | 適切な服装で過ごしているか | |||
| 好きなところにいる | 自由に移動できる環境があるか | |||
| 職員 | どこを向いているか | 入居者の見守りができる位置で作業しているか | ||
| 無駄話をしているか | 職員同士のコミュニケーションが活発か | |||
| 表情 | 入居者に向ける表情が穏やかか | |||
| 物の配置 | 椅子とテーブル | その人にあったテーブルや椅子を使用しているか | ||
| 動線 | 車椅子が通るのに邪魔のものが置いていないか | |||
| 入居者向け掲示物 | 高齢者が見やすい配慮があるか | |||
| 職員向け掲示物 | 管理が適切か | |||
| 内容は前向きか |
― たった数十分でも“深く見抜ける”3つの視点 ―
施設見学は、入居を検討するうえでとても大切な機会です。
ですが、短時間の見学で「本当にここでいいのか」を見極めるのは簡単ではありません。
そこでこの記事では、たった数十分の見学でも“その施設の考え方やケアの質”を感じ取るための3つの視点をご紹介します。
✅ 施設見学でチェックすべき3つのポイント
- 入居者の様子
- 職員の様子
- 物の配置(動線・設備・掲示物)
この3つを意識して見ていくことで、表面ではわからない施設の“中身”を感じ取ることができます。順番に解説していきます。
① 入居者さんの様子は“良い介護施設”の選び方の基本
▶ 肌の状態
高齢者の肌は非常に乾燥しやすく、保湿ケアは重要な日常ケアの一つです。
保湿が行き届いているかどうかは「丁寧なケア」が全体でできている施設かどうかのバロメーターになります。
→ 肌が白くなっていたり、体をかいている人がいないか確認しましょう。
1人見かけただけでは判断できませんので、必ず全体を見るようにしてください。
あわせて見ていただきたいのが、口のまわりや鼻の頭に乾いた食べ跡がついていないか、
と、目のまわりに固まった目ヤニがついたままになっていないかです。
この2つが揃っている場合、人手不足で日常的なケアが十分に行き届いていない可能性が高いと言えます。
▶ 髪の毛の整い方
日中でも何度も横になる高齢者は、髪が乱れやすいもの。
それをそのままにしているか、きちんと整えているかを見ることで、職員が「入居者を自分と同じように尊重しているか」が見えてきます。
▶ 衣服(膝掛け・上着)
高齢で活動量が少なくなるとみなさん寒さを訴える方多いです。
夏でも半袖より長袖を選ぶ方も多く、一年中ひざ掛けを手放さないなんて普通のことです。
ベッドにモコモコの上着のまま横たわっている人はいませんか?
寒そうに腕をさすっていいる人はいませんか?
私がバイトしたことのある施設の中には、職員の「面倒だから」という理由で、誰ひとりズボン下(肌着)を着ていないところもありました。
汚れたままの服や、前後ろ反対のお洋服の方が多いところは、人手不足で日常的なケアが十分に行き届いていない可能性が高いと言えます。
服装には、その施設での「生活の質」が表れます。
→ 全体的に暖かそうな格好をしている人が多く、清潔であれば、職員が充実し配慮が行き届いている可能性が高いです。
▶ 好きな場所にいられるか?
「誰もがテレビの前に並べられている」施設は要注意。(レクレーション直前は除きます)
人それぞれが思い思いに過ごしている(窓辺にいる、お部屋で寝ている、ウロウロしている、など)なら、個人を尊重するケアが行われている証拠です。
🔍 補足:身体拘束を見抜く視点
「ブレーキ付き車椅子で動けない」「ベルトで固定されている」ような方がいる場合、身体拘束が行われている可能性があります。
これは国が2001年から廃止を指導しており、正当な理由・委員会判断・家族の同意がなければ行ってはいけないとされています。
→ 新しく見える施設以外で拘束を見かけた場合は、要注意です。
実録!知らずに身体拘束をしていた新人時代の私
介護士1年目だった私は、オープン間もない施設で「バックブレーキ付きの車椅子」を使っていました。介助者には便利なこの車椅子も、自分で動ける入居者様には「不快」と注意され、使うのを控えていました。
しかし認知症で徘徊する方には「仕方がない」と使ってしまい、声かけが通じず、自分の仕事が進まない焦りから「これは拘束しても仕方ない」と思っていたのです。
⚫︎施設の取り組みで気づいた「拘束の事実」
1年後、施設で『身体拘束ゼロ』の方針が始まり、
・バックブレーキの撤去
・鈴の廃止
・拘束に関する勉強会
が実施され、私は初めて「自分が拘束をしていた」と気づかされました。
⚫︎身体拘束は3つの条件を満たさないといけない
厚労省が示す三原則は以下の通りです:
- 切迫性:本人や他者の命に関わる危険がある
- 非代替性:他に方法がない
- 一時性:すぐに解除する努力が継続されている
しかもこれらは現場の個人判断ではできず、「身体拘束防止委員会」などが判断する必要があります。
「仕事が終わらないから」は拘束の理由にはなりません。
⚫︎教育がなければ、知らないまま続けてしまう
新人の頃の私は、これらのルールを何も知りませんでした。ですが、施設全体で学び、ようやく「拘束とは何か」「なぜいけないのか」を理解できたのです。
この経験から、教育体制の重要性を痛感しています。
⚫︎ご家族様へ
身体拘束に対する考え方や、職員への教育体制は施設ごとに異なります。見学や面談時には、不安に思った点を遠慮なく質問し、納得できるまで確認することが大切です。
② 介護職員の対応から見る施設選びの重要なポイント
どこの施設でも『今日の夜勤は誰?』と聞いてくる入居者が必ずいます。
夜は人目が減るため、介護士個人のケアの質が露わになります。
例えば真夜中に入居者が、何か不安になって家に帰ると繰り返し訴えたとします。
A介護士 『夜なんですから寝て下さい』の一点張り
B介護士 温かいミルクを淹れてくれて数分話を聞いてくれた
C介護士 3回目以降のナースコールは全て無視
D介護士 自分の作業スペースに入居者を連れて行き、眠くなるまで一緒にいてくれた
これは全て私が見た実話の一部です。人それぞれ対応は数限りなく存在しますので、気の合う介護士が夜勤なのか気になるのは当たり前ですね。
高い志を持って丁寧に関わる介護士がどこの施設にも必ず存在しているのと同じ様に、
「自分がされたら嫌じゃないの?」と思うような対応をしてしまう、残念な介護士もまた
どこの施設にも必ず居ます。
ぜひ、見学時には、「志の高い介護士が働きやすい職場なのか」それとも「残念な介護士にとって居心地の良い場所になってしまっているのか」
――その“空気感”を感じ取っていただけたらと思います。
▶ 職員はどこを向いているか
介護度の高い高齢者を見守るには、数分おきの視線による確認が欠かせません。
見守りの必要がない方だけがフロアにいる場合でも、介護士は常に“耳のアンテナ”を立てながら作業しています。
入居者さんに背を向けて黙々と記録しているよりも、顔を上げれば全体が見渡せる位置で作業している職員の方が、安心感がありますね。
中には、入居者さんの席に混ざって記録をする職員もいます。
声をかけられて記録は進まなくなることもありますが、入居者さんからはとても喜ばれます。
▶ 会話・雰囲気
私が良い施設と思う施設の共通の特徴として、職員同士が活発にお話ししています。
ちょっとした私語や雑談も交えながら、風通しの良い関係があると、良いチームケアが行われていることが多いです。
そのような施設では介護士だけでなく、事務職や看護師、栄養士なども現場を通るたびに、静かに座っている入居者さんへ気軽に声をかけています。
一方で、職員同士でしか話さず、入居者には丁寧だけれど距離を置いた対応をする――これが“普通”の施設もあります。
こうしたお喋りが自然に交わされる施設は、残念な介護士には居心地が悪いかもしれません。
▶ 入居者への表情
見学者に対しての笑顔ではなく、入居者に向ける表情に注目してください。そこに、その職員の本質が現れます。
③ 掲示物・物品配置で判断する介護施設選びの視点
▶ 椅子とテーブル
不自然な高さの椅子やテーブルはありませんか?
背が低い、もしくは腰が曲がっている方が高いテーブルで窮屈そうにくつろいだりしていませんか。
▶ 動線
動線の悪さは介護士のストレスになります。
人がよく通るところに物が放置してありませんか?
使わないような荷物がたくさん積み上がったりしていませんか?
スムーズに移動できるかを観察してみてください。
▶ 入居者に向けた掲示物
車椅子の方が多い施設ならその目線で見やすい位置に貼ってありますか?老眼でも読めるような字の大きさですか?
これがクリアできている施設はあまりないのが現状ですが、まれに存在します。入居者の立場に立って考えられて、実行できる人が働いているんでしょうね。
▶ 職員に向けた掲示物
多くの施設では、ステーション(詰所)や冷蔵庫周辺などに職員向けの掲示物があります。
中には、まったく掲示物のないレアな施設もありましたが、ほとんどは何かしら貼られています。
掲示物のチェックすべきポイントは以下の通りです:
- 古い紙が重なって、内容が見えない
- 必要・不要が判断できず、貼りっぱなし
- 命令口調(例:〇〇厳守!、〇〇は何枚まで!)
- 異常に細かい指示が並ぶ掲示
こういった掲示が多い施設もあれば、以下のように整理されていて温かみのある施設もあります。
- 必要な情報だけがすっきり掲示されている
- 思わずクスッとするような、やる気が出る一言メモ
(例:「〇〇です、どうぞ」「いついつまでです。よろしく〜」など)
掲示物を見るだけで、そこにどんな人の集まりが働いているのかを垣間見ることができます。
ここまで心の目の準備が整ったら実際に施設見学を申し込んでみましょう。
施設選びの最初のステップ
ご家族が入居することになったとき、多くの方はまずパンフレットを取り寄せたり、施設のホームページを見るところからスタートされると思います。

しかし、そこに掲載されているのは基本的に「施設が見せたい情報」です。
✅「安心の〇〇体制」
✅「充実した〇〇サービス」
など、明るく優しい写真に添えられた言葉が並びますが、「こういう方はご遠慮いただいています」「実はこの対応は苦手です」といった本音は、まず掲載されていません。
口コミは参考程度に
Googleマップなどの口コミも一見参考になりそうですが、匿名性が高く、「職員の態度が悪い」「送迎車が荒かった」など、感情的な書き込みが目立ちます。
良い施設にもネガティブな投稿がつくことがあり、信頼できる判断材料にはなりにくいのです。
施設見学が“唯一の生きた情報源”
実際の施設の雰囲気を知るには、見学に勝るものはありません。気になる施設があれば、電話で「見学希望です」と伝えれば案内してもらえます。

決して玄関ホールの綺麗さや、充実した設備で「素敵なホームね」と思ってはいけません。
ここで重要なのは……
🌟1回、短時間だけの見学で決めないこと!
🌟できれば2回以上か、長い時間見学してほしい!
多くの施設では、1回目の見学で「施設の説明→少しだけ現場を見る→個室での入居相談」
という流れになります。
これはいわば「施設の得意な顔」を見せる時間。

ご本人様がこれからずっと暮らしていく場所ですから、1度の見学で決めるのは少し早いかもしれません。
いくつかの施設を見比べることで、「ここにしてよかった」と思える判断がしやすくなります。
現場の“空気感”を見るにはタイミングも大事
介護現場は、その時間帯の…
- 担当職員のスキルや心の状態
- 忙しさ・落ち着き具合
- 職員数や急な対応(救急搬送があったなど)状況
などによって、空気感がコロコロと変わります。
1回の見学では“その日の一瞬”しか見られません。だからこそ、複数回訪れることが、納得できる選択につながると考えています。
プロに任せると決めた今だからこそ
すでに自分の家族をプロに看てもらうというとても大きな決断をされた訳ですから「ここで良かった」と心から思えるよう、あと一歩だけ、見学・比較の時間を増やしてみる工夫をしてください。
それが、ご本人様やご家族様にとっても、あとからの「納得」と「安心」につながっていきます。
まとめ
今回は、施設見学で見るべきポイントと施設選びの初めのステップをご紹介しました。
①施設見学は直接施設にアポイントメントを取る。
②見学はなんとかして2回以上か、出来るだけ長めに。
分からない事は納得がいくまで現場の方に質問して大丈夫です。
③”施設見学でチェックするべき3つのポイント”を観察しつつ全体を見る
介護施設の選び方には、客観的な情報と「現場を見て感じること」の両方が重要です。
このページの情報が、みなさんの納得できる施設選びにつながれば幸いです。