「介護認定を受けたがらない親」にどう向き合えばよいのか。これは多くのご家族が直面する悩みです。
自分はまだ元気だと思っていたり、人の世話になることを嫌がったりする気持ちは自然な反応です。
しかし、そのままにしておくと、必要な支援を受けられず家族の負担も大きくなってしまいます。
この記事では、介護認定を受けたがらない親への向き合い方や説得の工夫、さらに認知症介護で陥りやすい誤解とその解決策を、現場経験や事例を交えながら解説します。
なぜ親は介護認定を受けたがらないのか
自然な拒否反応
「介護認定を受ける=弱った証拠」と思うお年寄りは少なくありません。
電車内で、高齢の方に席を譲ったら嫌な顔をされた。断られた。高齢の方が、子供連れの人に席を譲っていた。そんな経験はありませんか?
⚫︎「自分はまだ元気だから必要ない」
⚫︎「介護を受けるのは人に迷惑をかけることだ」
⚫︎「病人扱いされたくない」
こうした気持ちはプライドや自立心の表れであり、自分が反対の立場だったらと思うと同じ反応をするかもしれません。決して頑固だからではないのです。
対応策:説得より「気持ちに寄り添う」
力を貸してほしいと伝える
難しかもしれませんが、「あなたのために介護認定を…」と言うよりも、「私一人では支えきれないから力を貸してほしい」と、家族の大変さを素直に伝えるほうが受け入れられやすい場合もあります。
おすすめの方法としては、制度として伝える。
「健康診断のようなもの」
「年齢に応じて受ける決まりがある」と説明し、
“制度だから受ける”という流れにすると本人のプライドを守れます。
認定調査のときに気をつけること
介護認定の調査では、調査員を前に「私はまだ何でもできる」と張り切って答えてしまう方が少なくありません。
その結果、本当に必要な支援が伝わらず、十分な認定が受けられないことがあります。
実はこのような反応は誰にでも起こるもので、病院の先生や調査員もよく理解しています。
とはいえ、困っている家族としては「もっと実情を分かってほしい」とヤキモキしてしまいますよね。
そこでおすすめなのが、事前に家族が困っている点をメモにまとめておき、調査員に直接渡す方法です。
調査員さんも出来るだけ実情を汲み取りたいと思っているので迷惑になることはありません。
本人に気づかれないようにすることでプライドを守りつつ、実際の状況を正しく伝えることができます。
こうした工夫をしておくと、本人に合った介護認定を受けやすくなり、安心して支援につなげられるでしょう。
誤解しやすい認知症ケアの例
①「もう休んでていい」は逆効果!?
介護認定が下りたり、退職や子育てが一区切りつくことで役割を失うと、「自分はもう必要ない」と気力をなくしてしまう方は少なくありません。
家事や仕事から解放することは優しさの一つですが、同時に張り合いを奪ってしまうことにもつながりかねません。
たとえ社会での役割を終え、介護が必要な状態になったとしても、その人はその人らしく生き続ける存在です。
ほんの小さなことでも、本人にとっては大切な役割となります。
「まだ自分は誰かの役に立っている」という誇りを保ち、生きる力につながっていきます。
大事なのは「上手にできるか」ではなく、「誰かに必要とされている」と感じられることです。
実際に、料理の盛り付けを手伝ってもらう、
郵便物を受け取ってもらう、
庭の草花に水をあげてもらう
洗濯物を洗濯バサミに挟む
なんでも構わないのです。このような小さな役割が、日常に張り合いを与えます。
「ありがとう」「助かった」と声をかけるだけで、
人は自分の存在を肯定でき、
穏やかに人間らしさを保ち続けられます。高齢者だけでなく誰にでも共通する普通のことかもしれません。
穏やかな気持ちで過ごせることは、認知症の不安や混乱を和らげ、症状の落ち着きにもつながります。
全員に当てはまるわけではありませんが、試してみる価値は十分にあります。
役割は単なる作業ではなく、本人の尊厳を守り、家族とのコミュニケーションを深める大切な時間なのです。
②徘徊は必ずしも「問題行動」ではない
「徘徊」という言葉は、自分一人で帰って来られなくなる可能性があるので とても大きな問題に見えますが、 本人には理由があることがほとんどです。
徘徊といっても色々なパターンがあります。
⚫︎わからない歩き
目的があって出かけたのに目的を忘れてしまった。ここはどこ?
ウロウロするキョロキョロしている歩き方
このような場合には➡︎
本人に何に困っているか聞いてみると分かりやすいですが、きちんと説明できない場合もあるので、よく観察することが大切です。
トイレの場所がきちんとわかっているか?
発熱など体の不調はないか? など、不安になる原因を突き止めると、症状が治ります。
⚫︎わかってる歩き
「私は配達に行く」 「家に帰ってご飯を作らないと」など、使命感を持って出かけている状態なので、
いきなり否定したり、無理やり連れて帰ると症状が悪化することがあります。
このような場合には ➡︎
もし可能であれば、少し付き合ってあげるのが一番早く治る方法です。
ポイントは、否定はせずに共感を示す。 自分が世話をしている高齢者に話しかけるのではなく、一般の人と同じ対応が肝心です。
共感してもらえると、人はだんだん緊張が緩んできます。歩き疲れた、険しい表情が元に戻ったなどのタイミングで別の話題にして気を逸せたり、一緒にご飯食べに行きましょう。などと自然に方向を変えると、無理なく自宅へ戻れるケースが多いです。
一見遠回りのようですが、共感して受け止めることが最短の解決方法になることも少なくありません。
このほかに、単純にお散歩に出かけたパターンもありますので表情や仕草で見分けるか、優しく声をかけて本人の話を聞くといいです。
移動すること自体が高齢者の生活にとって大切な意味を持ちます。
足がむくんでいる。めまいがする。腰が痛い。など、運動不足からくる体調不良もたくさんあります。
危険が伴う場合もありますが、散歩や外出は体力維持や気分転換につながりますので可能な限り、ご本人様の好きなように対応してあげられるといいですね。
そこまでは手が回らないよという方には、介護保険外の自費訪問介護というサービスもあります。
介護の資格を持ったスタッフが丁寧に対応します
24時間・365日サービス提供
最短当日から利用可能で、利用時間は2時間から長時間までOK
認知症の方のケアに慣れたスタッフがマッチングされます
介護保険の申請が降りていなくても利用可能
迷ったら一度、無料相談だけでも試してみましょう。
\一人ひとりにコンシェルジュがつくから安心/
ヘルパー1万人以上・8万回以上利用されている実績と信頼
プロの介護士でも認知症理解は簡単ではない
経験による差
施設で働く介護士でも、認知症への理解度には差があります。
これは例えの話ですが、新人さんは、実際の認知症者の行動を見て戸惑いが多く、苦手に感じる人もいます。
中堅くらいに慣れてくると、冷静に受け止める一方で共感を忘れがになり、仕事をこなすために割り切った対応になっていきます。
そんな調子でなんとか騙し騙しでも認知症の人と一緒に過ごせるとベテランでも事務的に流してしまうことがあります。
それとは反対に、キャリアに関わらず、男女も問わず、元々優しい人であったり、熱心に勉強して認知症を理解しようとする職員も居ます。
そのような人は、ケア自体がとても暖かく献身的で、認知症の人にとても人気です。他の職員では拒否がひどいのに、この職員なら素直にお風呂に入ってくれる。
暴れさせないでケアが出来る。ということはよくある話です。
つまり、プロであっても認知症介護は難しいということかもしれません。
家族が「自分には無理だ…」と落ち込む必要はないと思います。
大切なのは、完璧に理解することではなく、日々の中で少しずつ学び、寄り添うことですしたくさんの人に支援をお願いしてテームで支え合うことです。
まとめ
親が「介護認定を受けたがらない」のは自然な気持ちです。
しかし、そのままでは家族の負担が大きくなります。
- 本人のプライドを守りながら制度を活用する
- 認定調査には事前の準備をする
- 小さな役割を持ってもらう
- 徘徊の背景を理解して寄り添う
そして、プロの介護士でさえ迷う世界だから、家族も一人で抱え込む必要はないということ。
困ったときは地域包括支援センターや医療機関に相談したり、介護保険外サービスの利用も有効的です。
認知症介護は「孤独な闘い」ではなく、支え合いの中で続けるものです。
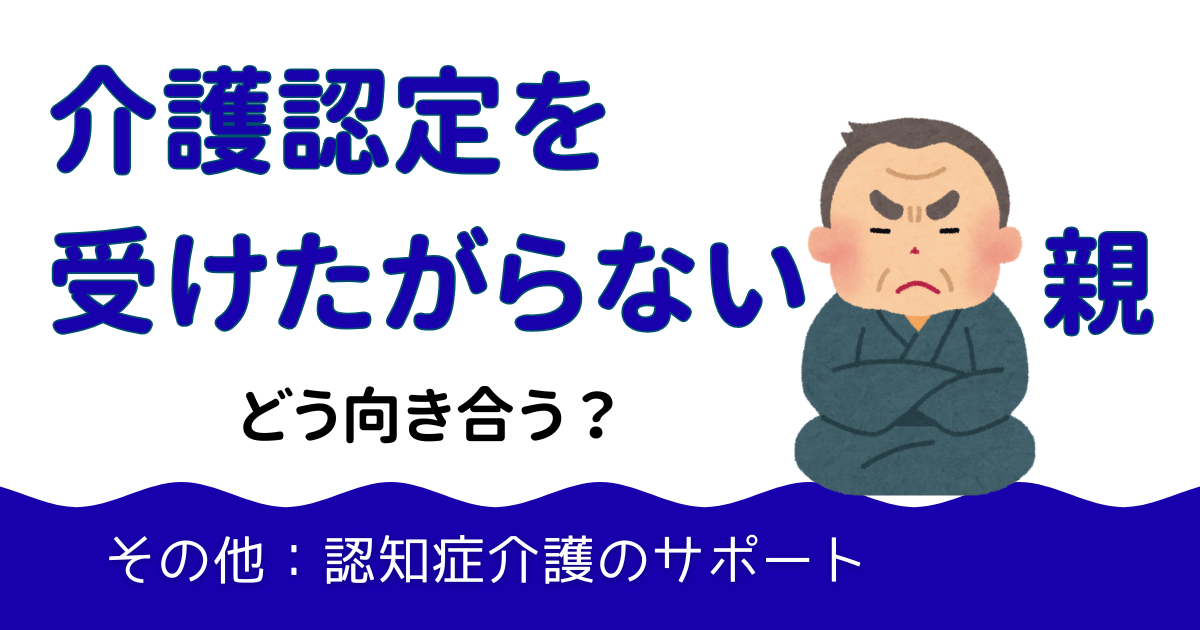
コメント