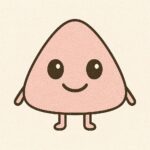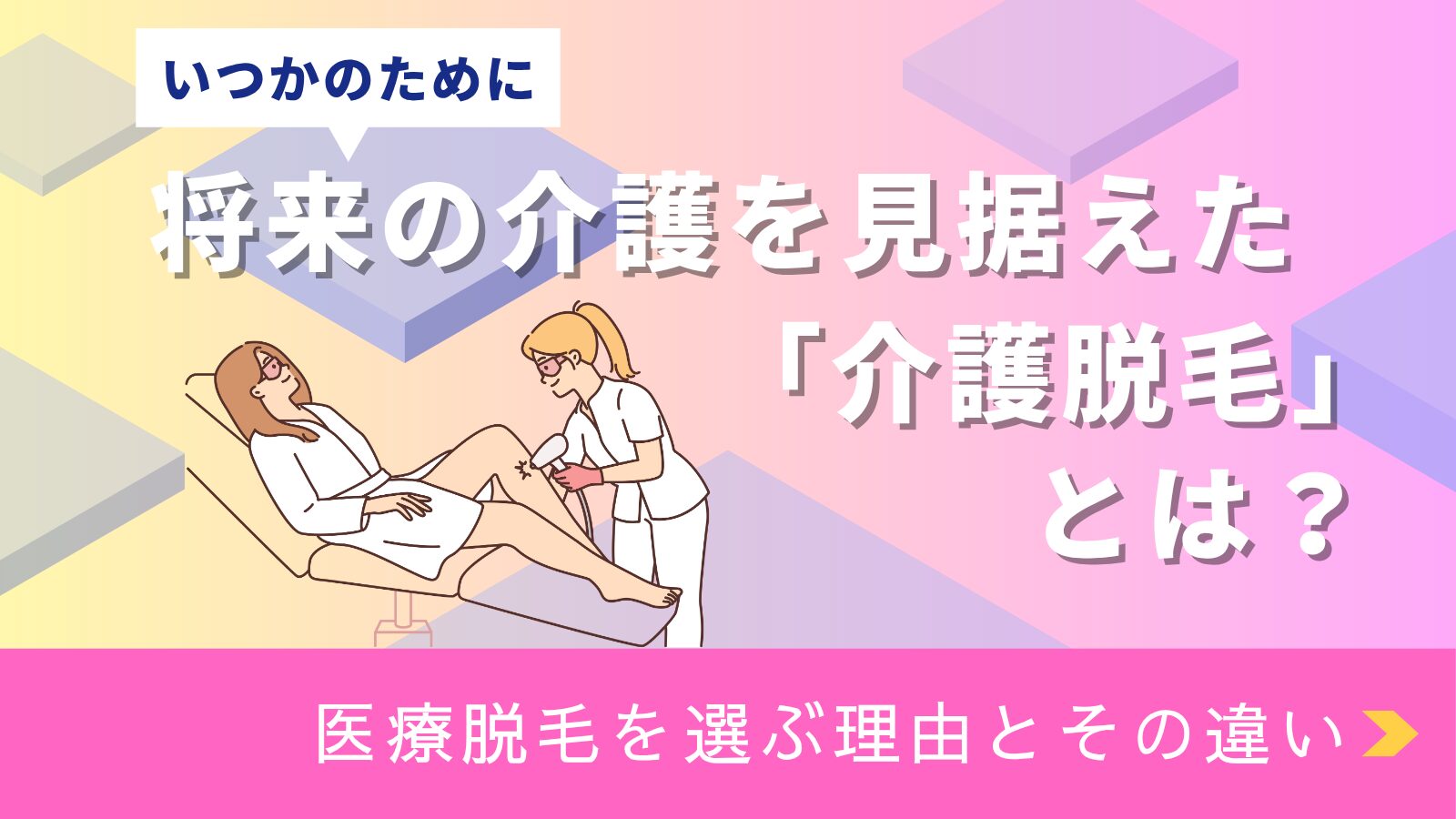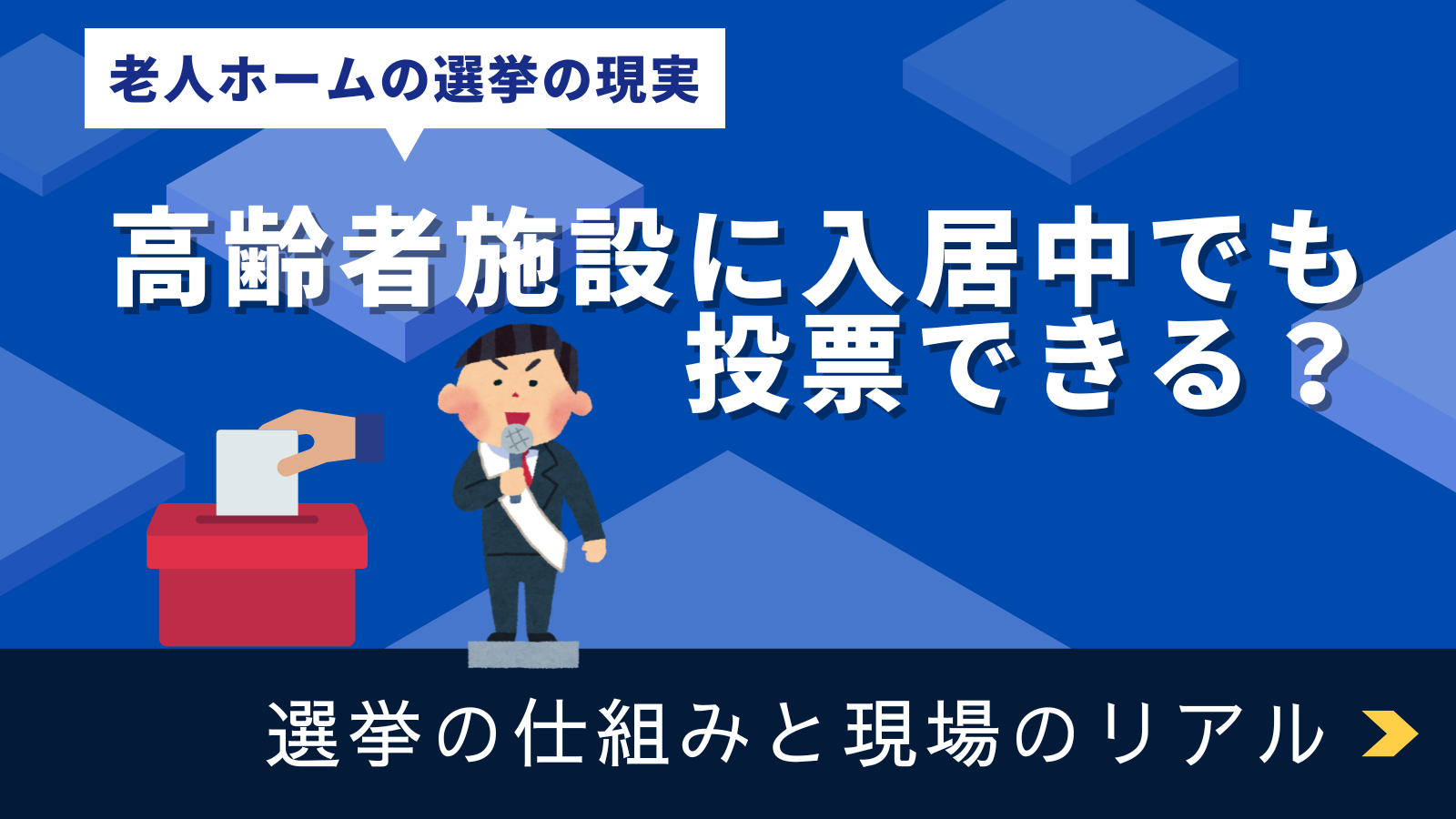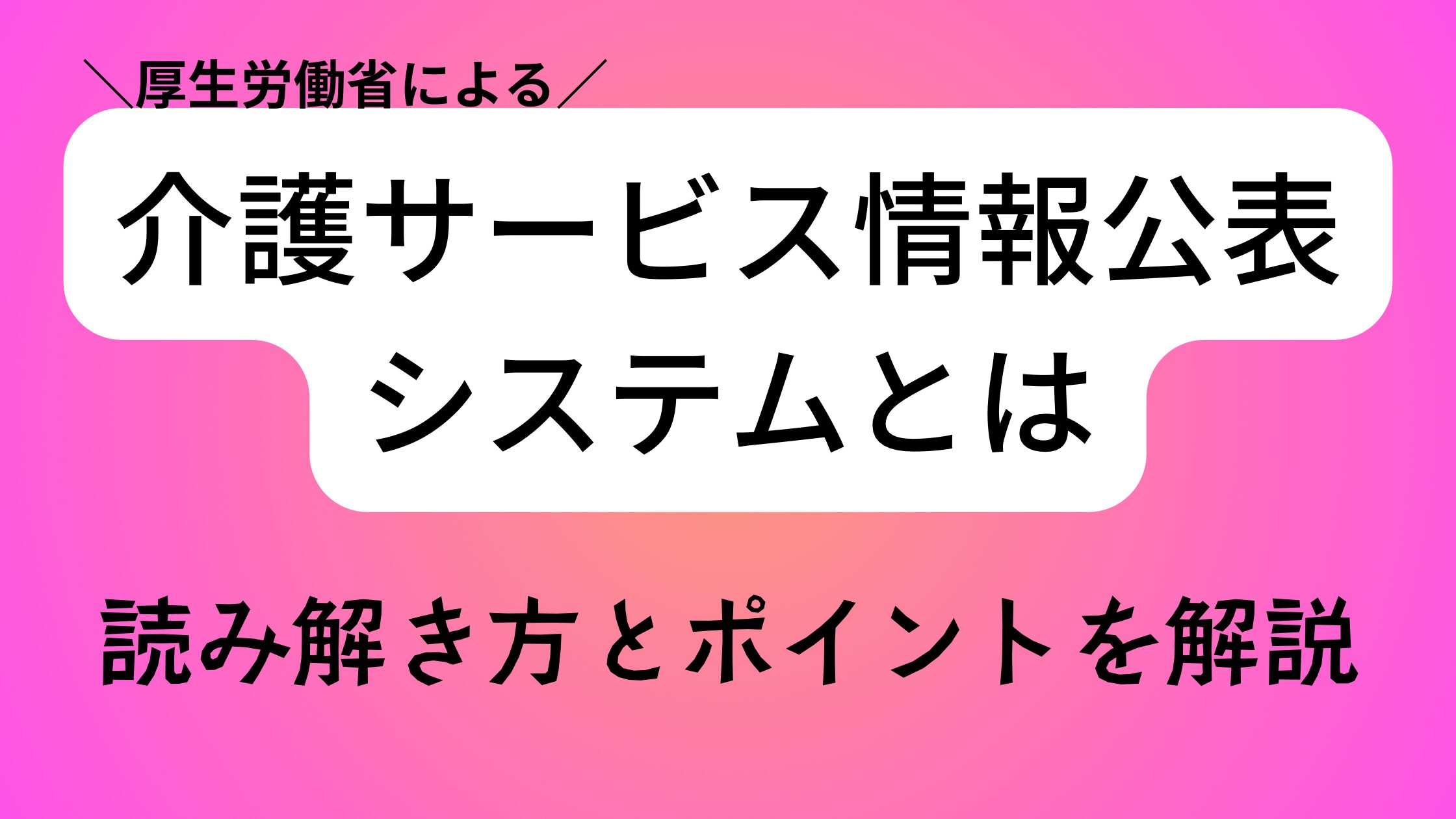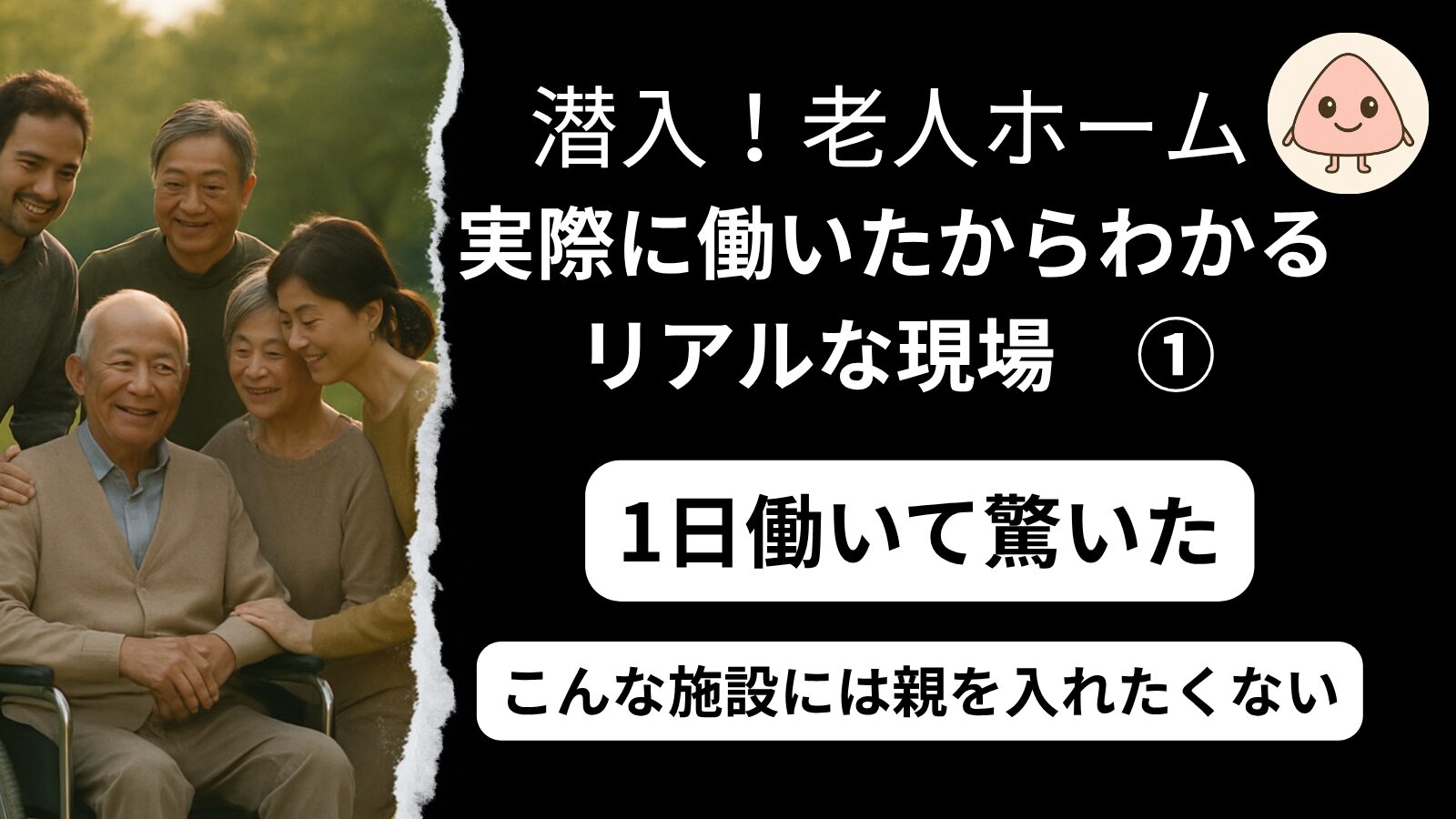私はこの施設に入りたい!初めてそう思った施設


大企業で沢山経営しているところがノウハウが揃っていそうで安心な気がするけど実際はどうなのかな…
この記事は、全国700ケ所以上で介護事業を展開する企業の有料老人ホームに
介護士として100時間以上勤務した短期バイトの経験の共有です
☑️この記事でわかること
- 昼間のフロアでの様子
- お風呂での様子
- 入居者さんが語ってくれた本音
- 現場スタッフが抱える思い
- ベテラン介護士から見たこの施設の特徴
- 総評
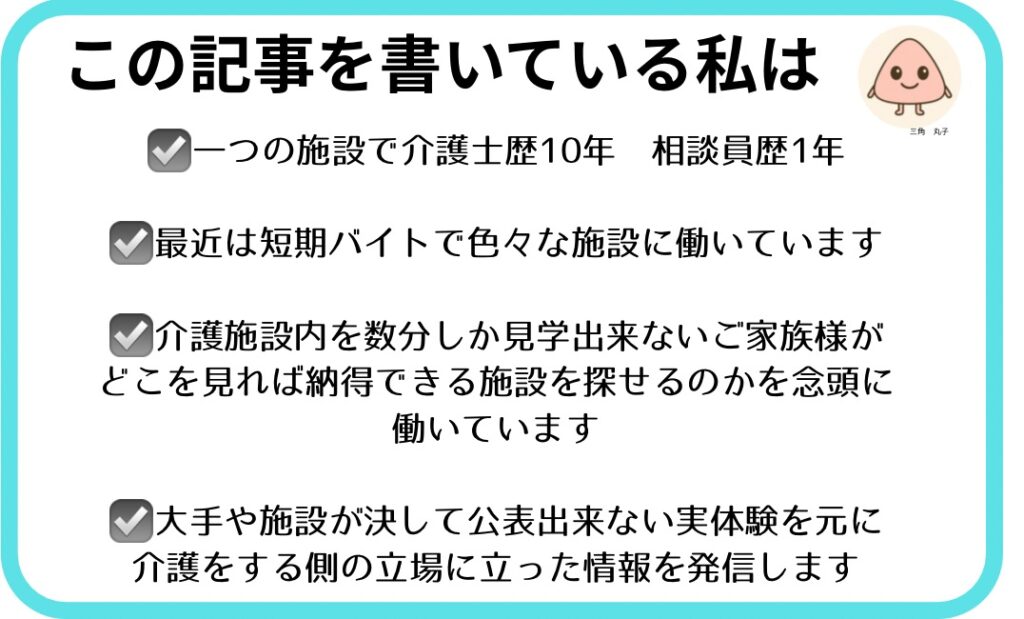
このレポートの前提
私が介護士として勤務した地域は人口約69万人、高齢化率21.3%。
つまり、約5人に1人が高齢者という高齢社会です。
このエリアには特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームが150件以上存在します。
その中の1つ、大手民間企業が運営する有料老人ホームでの勤務体験を基にした記事です。
※施設が特定されるのを避けるため、数値など一部は意図的にぼかしています。
記載している内容はすべて私自身の実体験に基づくもので、リアルな現場の空気をそのままお伝えしますが、私的な表現であることご理解お願いします。
施設の特徴と運営母体
この施設を運営しているのは、資本金6億円以上の大企業。
医療の分野からスタートしたこの会社は医療事業・介護事業が得意分野で、
実際に働いた有料老人ホームでも、自立の方から入居できて、医療依存度が高くなっても受け入れられるということと、リハビリが充実していることが売りの施設です。
入居率は80%台と高水準を維持
第一印象:「1日だけでもここで働けてよかった」と思えた瞬間
私がこの施設で初めて働いたのは、1日単位の短期バイトとしての勤務でした。
それにも関わらず、開始早々30分もの研修が用意されていたことにまず驚きました。
内容は「高齢者虐待の防止」や「怒りのマネジメント」など、介護の質を左右する重要なテーマ。
さらに、しっかりと作り込まれた研修資料と、参加者全員に対してきちんと時給が支払われているという姿勢。
「次回勤務するかもわからないスタッフにここまで?」と、本気の教育体制に感動しました。
いきなり1人で排泄介助を任されても安心だった理由
この施設での初仕事は、寝たきりの入居者さん数名のおむつ交換。
現場の職員さんが1分程で手順を説明してくれました。
初めてなのに職員さんがついてくれないということに、当然不安はありましたが、
その説明が的を得ていて、最小限。
分からなくなればまた、聞けば良いと思って作業を始めましたが
最初の説明だけで、どの入居者さんん介助も不安なく対応することができました。
「すごい。こんな施設があるんだ……」
新人教育に何ヶ月もかける施設にいた私には新鮮な驚きで興奮する体験でした。
情報共有の工夫:始業前ミーティングの質が高い
この施設には6つのフロアがあり、勤務開始前には一つのフロアに職員が集まり、
当日の情報を共有するミーティングが行われます。
ざっくばらんな雰囲気ながら、交わされる会話のほとんどは業務に関すること。
職員同士の活発な意見交換からは、良い人間関係と前向きな空気が感じられました。
特に印象的だったのが、ホワイトボードの使い方と情報の整理整頓。
職員配置や1日の予定が視覚的にわかるように示されており、必要な書類も整っていて探す手間がありません。
これはまさに、「業務の見える化」と「仕事の体系化」ができている証拠です。
体系化のイメージ
🔹 体系化されていない職場
→ 「このやり方って誰に聞けばいいの?」「人によってやり方がバラバラ」
🔹 体系化されている職場
→ 「マニュアルがあって読めばすぐ分かる」「誰がやっても同じレベルでできる」
日常の現場の動き:適切な指示と明確な役割分担
始業時間が近づくと、リーダーや主任などの職員から全体に指示が出されます。
単発バイトも、担当するフロアの入居者さん一人ひとりの特徴や介助の注意点をまとめた一覧表を受け取り1人で業務に入ります。
1人業務が終わると、施設職員さんについて、フロア業務や入浴介助のお手伝いを行うのが大体のパターンです。
「1人での業務が終わったら、何階に行ってくださいね。そこには〇〇という職員がいます。」
と、そこまで教えてくれるところは他には見たことがありません。
🔄 他施設との違いが浮き彫りに
私が過去に勤務した多くの施設では、次のような状況がよく見られました。
- 一つの業務(例えば排泄介助や配膳など)を終えた後、
次に何をすればよいかわからないし勝手には何もできない - 次の指示を仰ごうと職員さんを探し回る
- その職員さんが個別ケア中で見つからない
- その間、ただ立っているしかない時間が発生する
つまり、作業が体系化されていないために、バイトや新人が現場で浮いてしまい、人件費や時間の無駄になっています。
こちらの施設では1日単位のバイトでも問題なく即戦力にできるので、リピーターのバイトさんが多く、居心地の良さが伺えます。
フロア(昼間)の様子::広さと自由さが両立する空間設計

この施設では、すべての入居者さんが個室に入居しています。
各部屋にはトイレと洗面台が完備されており、プライバシーと自立支援の両方に配慮された造りです。
共用スペースとなるフロアには、
- 職員用のキッチンとカウンター
- 入居者さん全員分以上の座席
- 娯楽室のように広々としたスペース
が設けられています。
陽の光が差し込むこの空間は、特別な用途が決まっているわけではありませんが、自由に過ごせる「余白のある環境」としてとても印象的でした。
テレビは見たい人だけでOK。個別対応が可能な設計
フロアが非常に広いのですが、設置されているテレビは1台のみ。
全員が同時に視聴できません。
「テレビを見たくない方にも配慮できる」
それがかえって利点になっていると感じました。
つまり、個別の過ごし方に対応しやすい環境設計だということです。
静かに過ごしたい方、談笑したい方、それぞれが心地よく共存できる空間が整っています。
生活リズムも対応力も◎ どの職員が担当でも変わらない安心感
自身で選択できない人に対して、起こしっぱなしや寝かせっぱなしにせず、
何度も寝たり起きたりを繰り返すのが当たり前のように行われています。
また、どの職員が担当してもフロアの雰囲気に大きな差がないのも特徴です。
指示や連携、職員の数の余裕がしっかりしているからこそ、安定した対応ができているのだと感じました。
お風呂での様子:安全・清潔・ケア体制

この施設では、各階に浴室があるにもかかわらず、稼働しているのは一つのフロアのみ。
そこに介護職員が集合して入浴介助を行います。
入浴介助の体制は以下の通りです:
- 浴室内に職員2名
- 脱衣と移動を担当する職員が3名
- 常時2~4名の入居者さんが同時に入浴
合計5名のスタッフが連携して動くことで、安全性と効率性を両立した体制が保たれていました。
プライバシーと安全性のバランス
一見すると「職員が複数いる中での入浴なんて、プライベートがない」と感じるかもしれません。
しかし、職員と入居者さんが1対1になる場面が極力ないように配慮されているのは、非常に重要なポイントです。
というのも、介護現場では「特定の職員の裁量に任せるケア」が常態化すると、
やがてケアの質に差が生まれ、施設全体の風土が乱れる原因になることがあります。
ここでは常に複数人での介助を徹底しているため、安全性・透明性・公平性が担保されていました。
これは、介護の質を高く維持するための重要な姿勢だと感じました。
全身保湿が当たり前。細部まで清潔なケアに驚き
さらに驚いたのは、入浴後のスキンケアの徹底ぶりです。
この施設では、入居者さん全員が「全身保湿は必須」という前提でケアされており、
肌が乾燥している人は見当たりませんでした。
- 足の指の間
- 拘縮で肌同士が重なってしまっている部位
これらの見落とされがちな部分まで清潔が保たれ、保湿がされていて
スタッフの観察力と丁寧な対応が光ります。
最小限の動きで最大のケア効果を実現
「誰がやっても同じクオリティ」が担保されるようにここでも工夫が見られました。
- 無駄な動きがなく、流れるように動線が整っている
- 手順が決まっていて、どこで誰が何をするか明確
- 情報共有が事前にされており、個別ケアも安心して任せられる
結果として、漏れや抜けがなく、スピーディーかつ丁寧な入浴ケアが実現されていました。
入居者さんが語ってくれたこと:不満の声が聞こえない理由

この施設には、認知機能がしっかりしている入居者さんも多く、
短い勤務の中でもいろいろな方とお話しする機会がありました。
話してくださる内容の多くは、ご自分の過去のことやご家族の話、趣味の話など。
そして驚いたのは、施設や職員に対する不満が一切出てこなかったことです。
高齢者施設では、日々のちょっとした不満や不安が話題に出ることも多いのですが、
ここではそれが全くありませんでした。
これは職員との信頼関係が築かれている証ではないかと感じました。
フラワーアレンジメントとドライフラワー。生活に彩りを添える工夫
フロア内には、季節の花がさりげなく飾られていることが多く、
ある入居者さんに伺うと「月に1回、フラワーアレンジメントのイベントがある」と教えてくれました。
その際に使ったお花は、
- ドライフラワーにして再利用
- 職員と一緒に手入れして長く楽しむ
といった工夫をされており、生活に彩りを与える丁寧な関わりが感じられました。
移動販売や外出支援も。日常を大切にする取り組み
そのほかにも、
- 職員付き添いでのスーパーへの外出
- 施設内への移動販売(衣類・パンなど)
といったイベントもあるそうで、皆さん楽しそうに話してくださいました。
「パン屋さんが来る日は朝からワクワクするのよ」
そんな何気ない言葉の中に、施設での暮らしに満足されている様子が垣間見えました。
イベント情報は誰にでもわかりやすく
施設では、1ヶ月分のイベントスケジュールが一覧表になって掲示されています。
掲示場所も工夫されていて、
- 各フロア
- 必要な方の居室内
- 施設の入り口
と、どの立場の人にも見やすい場所に貼り出されていました。
こうした情報共有の姿勢も、安心感や参加意欲につながっているように思います。
職員が語るリアルな声:気になっていた5つの点を聞いてみました

施設の内側を知るうえで、現場で働く介護職員の声はとても重要です。
私は事前に調べていた「介護サービス情報公表システム」やインターネット上の情報をもとに、
以下の5つの疑問点について、正職員の方に率直に質問してみました。
① 派遣職員はいるのか?|42.2%が派遣
厚労省のデータと実際の現場とのギャップを確かめるために、
職員の雇用形態について質問しました。
答えは
「全体の42.2%が派遣職員です」
つまり、実際の業務を支える人員の約半数が派遣スタッフという現状でした。
これは人手不足の介護業界において一般的ではありますが、離職率の見え方に影響するため、
データを読む際には注意が必要です。
② 勉強会はあるのか?|全員ではないが月1回タブレット研修あり
公表システムのレーダーチャートに「研修の項目」が低評価だったことが気になり、
実際の研修体制を質問してみました。
回答は以下の通り:
- 本社で大規模な研修が実施されているが、全職員が出席するわけではない
- 一般職員はタブレット端末で月に1回、eラーニング形式の研修を受けている
つまり、研修機会はあるが、対面での深い学びが全員に保障されているわけではないという印象です。
数値で見る評価との一致も見えてきました。
③ 入居者のお金の管理はどうなっている?|原則は請求書払い
日用品の購入や外出の自由度が高い施設なので、
「お金の管理が大変なのでは?」と感じていました。
これについては、
- 自分で管理できる方のみが少額の現金を持つ
- その他の方は基本的に施設側が把握し、請求書払いで対応
とのことでした。
職員が金銭管理に煩わされず、ケアに集中できる体制が整っているように見受けられました。
④ 退去率が14%と低い理由は?|偶然の可能性が高い
介護サービス情報では退去率14%とかなり低めの数値が出ていましたが、
実際に聞いてみると、
「たまたま今は少ないだけかもしれません。入退院を繰り返している方も複数います」
とのこと。
⑤ 体系化が上手な理由は?|「リーダーがすごい」の声多数
あれほど仕事が整理され、誰がやっても同じ質で回る現場。
「なぜここまで体系化できているのか?」という疑問に対して、
最も多く聞かれた答えは、
「リーダーがすごいんです」
でした。
日々の業務の変更点を職員全員にどのように周知しているのか教えて欲しいですがそこまではわかりませんでした。
現場職員の口から自然とこの言葉が出るのは、信頼されているリーダーの存在があるからこそ。
職場の安定感はトップの力量に左右されるというのは、介護の現場でも強く感じられる部分です。
ベテラン介護士から見たこの施設の5つの特徴

これまでいくつもの介護施設で働いてきた私にとって、
この施設は、明らかに他とは違う「強み」がいくつもある施設でした。
単なる現場の雰囲気の良さではなく、
「なぜこの施設がうまく回っているのか」
という本質的な理由が、いくつも見えてきました。
① 仕事の効率化がすごい|インカムが活躍する仕組み化の現場
まず驚いたのは、仕事の体系化と効率化のレベルの高さです。
この施設では、ほとんどの職員が「インカム(トランシーバー)」を常時装着しています。
- 玄関から「ご家族が来られた」「医師が来訪」などの情報が全員の耳に届く
- 入浴中でもその場を離れずに看護師を呼ぶことができる
など、情報伝達が即時かつ無駄がない。
そのため、たとえば訪問者がエレベーターで移動して、居室に到着する頃には準備が整っているなど、現場での連携が非常にスムーズです。

② 人件費を惜しまない|人が足りているという贅沢
経営面の詳しいことは分かりませんが、
この施設では人員シフトに関係なく1日バイトを毎日募集しています。
「今日は人が余ってるな」と感じる日があるほどです。
それでも募集を止めないのは、常に人に余裕を持たせた運営をしている証拠です。
職員側は、毎回初めて会うバイトに手順を教えたりと大変そうですが、
何度か来て慣れている人がリピートで勤務することで、現場の流れはどんどんスムーズになります。
また、掃除・洗濯・調理・食器洗いなどは全て専門スタッフが担当しており、
介護士は介護業務に専念できるのも大きな特徴です。
※過去に私が勤務していた施設では、食事の盛り付け、洗い物、掃除、洗濯、シーツ交換、家族対応…すべて介護士1人が担っていました。
この差は、現場の負担感・介護の質・離職率すべてに直結します。
③ 改革が速い|「それ、片付けよう」の行動力
施設によっては、「誰のものかわからない私物」「使ってない備品」などが溜まりがち。
しかしこの施設では、
「〇日までに片付かないものは処分します」
といったルールが徹底されており、迷いなく整理・改革が進みます。
休憩室や、作業場のレイアウトが頻繁に変わったり、不要なものが一掃されたり、
とにかく風通しの良い空気と、スピード感ある運営方針が見られました。
④ 休憩室は“働く人”の交流の場|雑談が連携につながる場所に
感染症対策の観点から、他施設では「一人一卓」「背を向けて休憩」などの工夫がされていますが、
この施設では違います。
- 大きなテーブルを囲むように職員が休憩
- 換気を徹底し、食事時以外はマスク着用
- テーブルの周囲にはソファが複数配置され、横になって休む人も
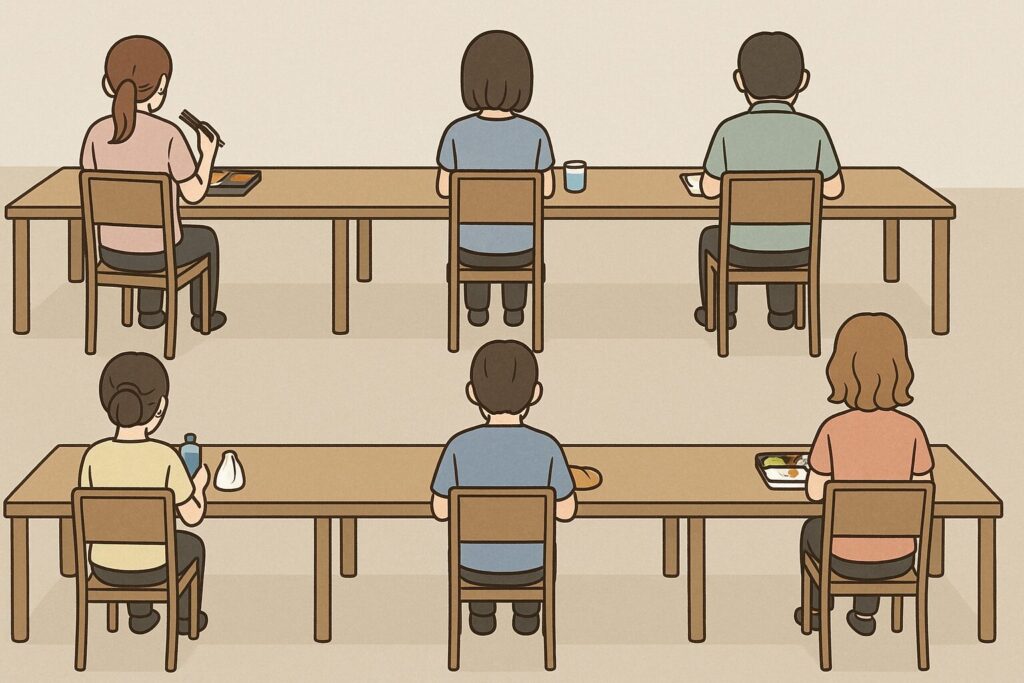
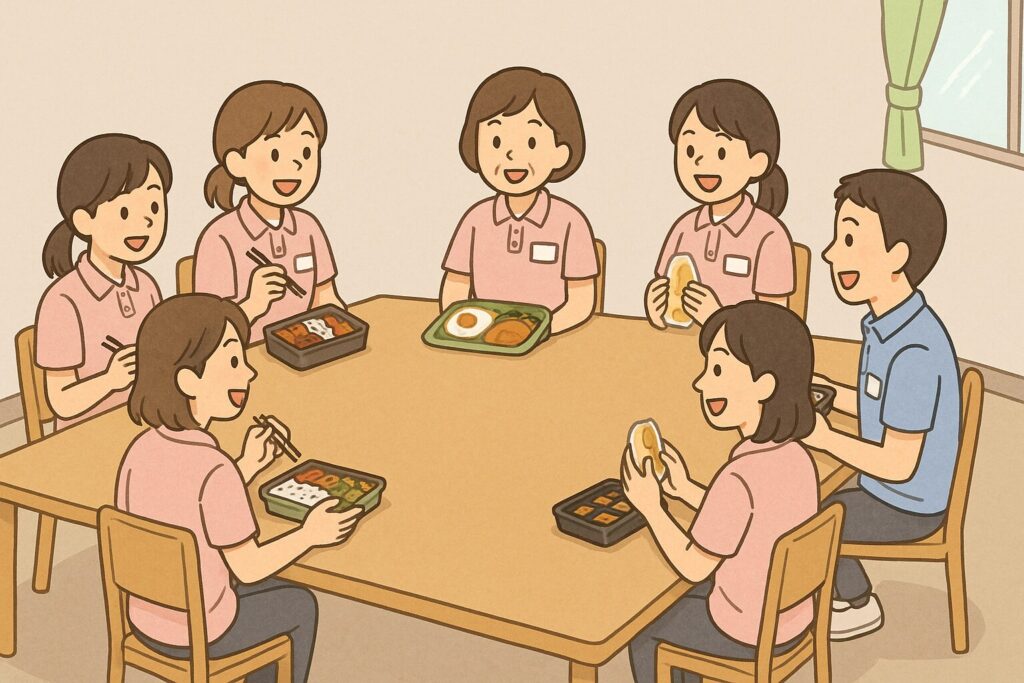
さらに、休憩室でもインカムの音声がスピーカーから流れており、現場の状況を把握できます。
だからこそ、気になる業務の話や疑問、ちょっとした愚痴も自然に話せる空気ができている。
こうした日常のコミュニケーションの積み重ねが、強固な連携力を生んでいると感じました。
⑤ リーダーの存在感が全てを底上げしている
この施設の職員たちの会話から、何度も聞こえてきたのが
「リーダーがすごい」という言葉。
- 「インカムだけでなく、個人宛にメモで指示をくれるので迷いがない」
- 「あの人みたいになりたいと思ってる」
- 「リーダーがいないときも回るようにしてるけど、やっぱり違うよね」
など、リーダーへの信頼と尊敬が職場全体に根付いているのが印象的でした。
他の施設では、「主任って誰?」「尊敬されていない上司」も少なくありません。
それに比べてここでは、職場の中核に明確な“軸”がある。
これが、この施設の組織としての安定感と成長力の源になっているのだと思います。
総評|ここなら「自分も親も入居したい」と思える数少ない施設
実は、同じグループ会社が運営する別の施設でも働いた経験があります。
しかし、そこで感じたのは、
「この施設が特別にうまくいっている」
という事実でした。
つまり、グループ全体の方針が素晴らしいというより、現場の工夫と人の質の高さがこの施設を支えているのです。
人の良さが「異常値レベル」
職員の方々は、とにかく人当たりがよく、協力的な人が多い。
日々の業務に余裕があり、チームとしての関係性がうまく築けているからこそ、
誰かが困っていれば自然に手を差し伸べる雰囲気ができているのだと思います。
「ここなら自分も、親も安心して入居できる」
そう心から思える、数少ない施設でした。
入居者さんの状態も良好
実際に勤務してみて感じたのは、
- 皮膚の状態がよい(乾燥や褥瘡が少ない)
- 整容が整っている(髪・服・清潔感)
- 汚染対応が迅速かつ丁寧
といった、ケアの基本が徹底されていること。
これは、「施設の方針」「人員体制」「教育レベル」すべてがかみ合ってこそ実現できるものですが、結局は人次第だと痛感する体験でした。
あわせて読みたい老人ホームに入居する事を決めた今!ミスマッチを減らす方法 の中で紹介している、チェックリストによる評価表も載せておきます。
| 入居者の様子 | 肌の保湿 | 肌が乾燥していないか全体に確認 | ◎ | 全員ツヤツヤ〜普通肌(いつでも) |
| 髪の毛 | 髪の毛が整っているか | ◎ | 美容室帰りの様な方もおられます(職員がやる) | |
| 膝掛けや上着 | 適切な服装で過ごしているか | ◯ | 上着、膝掛けなどオンオフがしっかりしています | |
| 好きなところにいる | 自由に移動できる環境があるか | ◯ | エレベーターにロックがかかっていません | |
| 職員の様子 | どこを向いているか | 入居者の見守りができる位置で作業しているか | ❌ | 施設の作り的に背中を向ける位置にしか作業テーブルがありません |
| 無駄話をしているか | 職員同士のコミュニケーションが活発か | ◎ | とにかく会話が活発です | |
| 表情 | 入居者に向ける表情が穏やかか | ◎ | ただ通り過ぎれば良いのに一言声を掛けたり、しゃがんで無駄話をしたりします | |
| 物の配置 | 椅子とテーブル | その人にあったテーブルや椅子を使用しているか | △ | テーブルは高さの変更が効かない物ですが、車椅子などで調整している様です |
| 動線 | 車椅子が通るのに邪魔のものが置いていないか | ◯ | 全体に広いので動線は問題ありません | |
| 入居者向け掲示物 | 高齢者が見やすい配慮があるか | ◯ | 食事メニューの文字が小さく、高い位置にありましたが、レクレーション予定が各部屋にあったりと配慮が見られます | |
| 職員向け掲示物 | 管理が適切か | ◯ | 書類が必要最低限で、フロアには紙類がなく休憩室で閲覧する仕組みでした | |
| 内容は前向きか | ◯ | 高圧的は注意書きはありません |
ひとつだけ惜しいポイント
ひとつだけ気になった点を挙げるとすれば、
職員の座る椅子が、入居者さんに背を向ける位置にしか置かれていないということ。
ここはケアの「目」が届きにくくなる構造上の課題であり、
チェックリストでは❌評価としました。
とはいえ、それを補って余りあるほどの◎評価が並び、
総合点では群を抜いた高得点施設となりました。
次回レポートもお楽しみに!
今後も、こうした実際に働いて分かった施設のリアルをレポート形式で発信していきます。
ブックマークして活用してくださいね。
皆様の施設選びが、納得のいくものとなりますように。